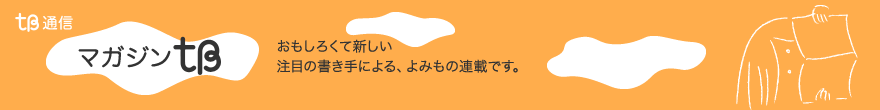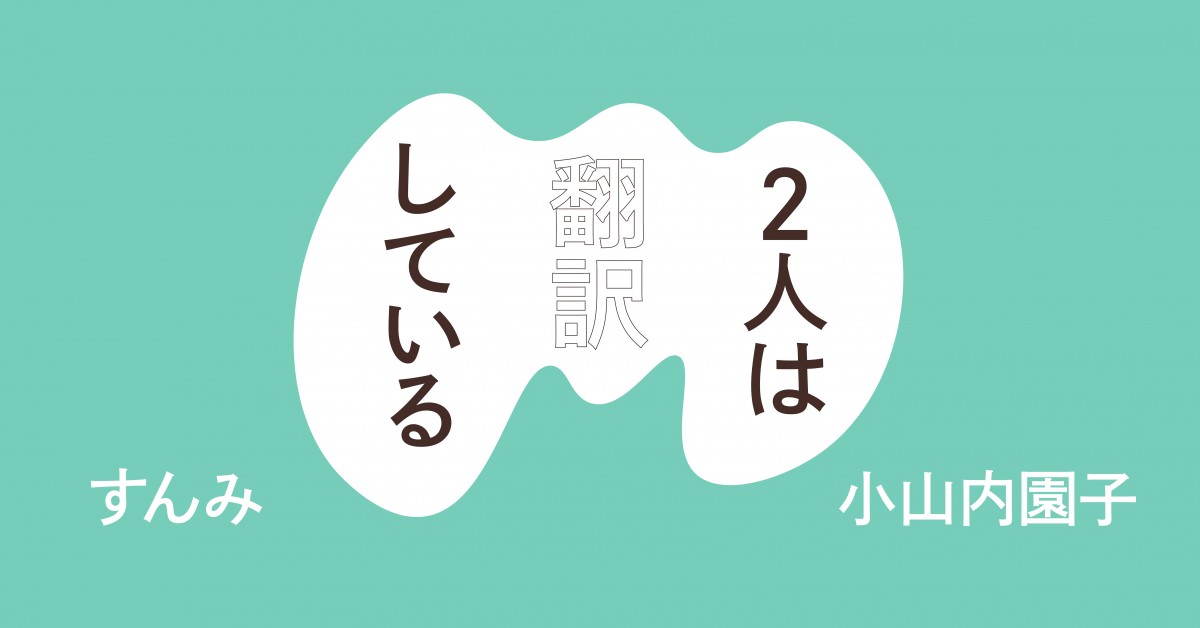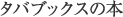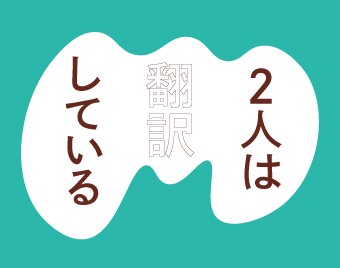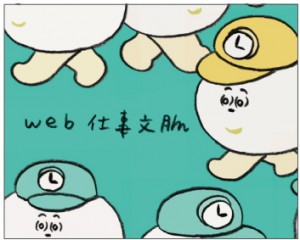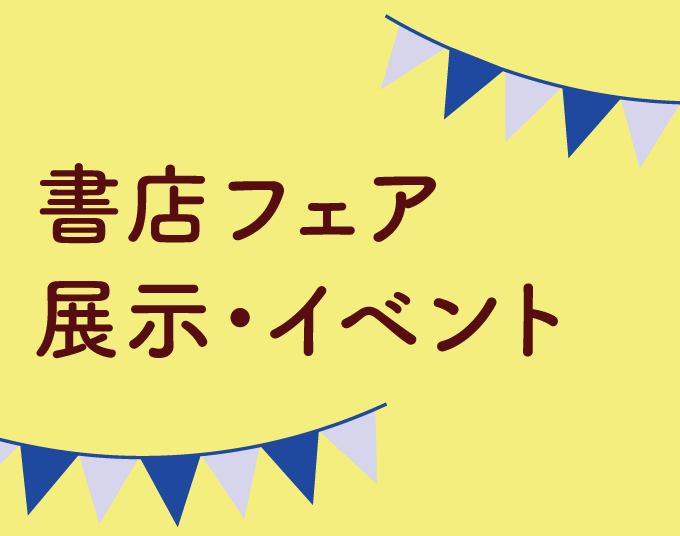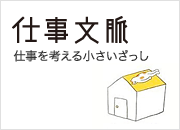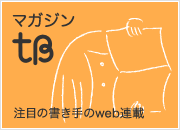ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
(2025/8/22)
前編はこちらです
***
ソーシャルワーカーとして立て続けに面接相談を受けた日も、帰宅してからの翻訳作業がよく進んだ。
面接相談はだいたい1時間程度。顔を合わせて話を聴く。制度の案内とか、書類を作成する手伝いとか、飲んでいる薬を一緒に確認しながら小分けにするとかの作業であれば、何かをやり遂げたような気分にもなって、わりと爽やかに終わる。だが、だいたいの相談は、ひたすら相手の話を聴くものだった。私自身は「全身全霊で傍(そば)にいる」という覚悟だったけれど、それこそ傍(はた)から見れば「斜め向かいでボーっと話を聴いている人」でしかなかっただろう。全身全霊とはつまり、こんな感じだ。
相手がぽつりぽつりと語る言葉を聴きながら、私の頭の中でその人を映像化する。たとえば、かつて夫から暴力を振るわれた記憶が、今も消えなくてつらいという相談。相談者が、その出来事のことを語り出す。時間帯。場所。天気。赤ん坊が激しく泣いていた。ブーンと回る扇風機の機械音だけが響いていた。話は時系列では進まず、突如として生々しい場面が挿入されもする。断片的だったり、曖昧だったり、辻褄が合わなかったりの言葉がつなぎ合わされて、気がつくと私の頭では、1本の映画のような映像ができあがる。物語が立ち上がる。はじめて、相手をとらえた気がする。語る声は、大体において小さくて、抑揚が少なくて、低かった。
誰かの話を全身全霊で聴いた日は、とにかく翻訳が進んだ。体はへとへとなのに、時間的な余裕があるときよりはるかにページが進む。一体何なんだろう。自分でもよくわからない。ただ、そういう日は、テキストから聴こえてくる声が普段よりひときわ鮮明な気がした。小説家というプロが綴った物語であるぶん、昼間に会う人より通った「声」になるのかもしれない。韓国文学について、よく「声を上げている」と言われるが、私は実は「声が聞こえる」文学だと思っている。社会の騒音にかき消されがちな声、自分の胸の中でだけで渦巻きがちな物語を、非常にクリアに奏でてくれる文学。
そういえば、最近読んだ韓国の小説も、そんな1冊だった。カン・ファギルの4年ぶりの長編『治癒の光(치유의 빛)』で、登場するキーワードはなかなかに刺激的だ。超肥満体の女子中学生、スクールカースト、宗教二世、突然襲う痛み、謎の治療施設……。だが中身には、各人が自分の物語にすがって生き抜こうとする切実さと、自分で自分の物語を信じきれなくなる絶望があますことなく描かれている。世の中は単純ではない。超肥満体の女子中学生はクラスで軽んじられているが、一方で新興宗教の信者の子であるクラスメイトに憐れみを向ける存在でもある。簡単な割り切りを許さないからこそ、物語が増幅し、相克し、それぞれの声が極まる。
臨床心理学者の河合隼雄は、作家の小川洋子との対談『生きるとは、自分の物語をつくること』で、こう言っている。
「人間は矛盾しているから生きている。全く矛盾性のない、整合性のあるものは、生き物ではなくて機械です。命というのはそもそも矛盾を孕(はら)んでいるものであって、その矛盾を生きている存在として、自分はこういうふうに矛盾してるんだとか、なぜ矛盾してるんだということを、意識して生きていくよりしかたないんじゃないかと、この頃思っています。そして、それをごまかさない」
矛盾をはらんだ存在の、断片的で曖昧な小さい話。きっと私はそれを、翻訳作業の原動力にしているんだろう。
今、日本の社会では、わかりやすくて、白黒はっきりしていて、誰かの存在を断罪するような「大きな物語」が幅を利かせつつある。怖い。小さな物語が大きな物語にのみこまれるから怖いというだけではない。ささやかな物語を紡いでいたはずの人々が、誰にも耳を傾けてもらえない絶望から、大きな物語に自ら身を投じているのではないかということが怖い。誰かの生きるよすがになるささやかな「物語」に耳をすませることは、もしかしたら私なりの、「大きな物語」「大きな声」への抵抗かもしれない。
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子