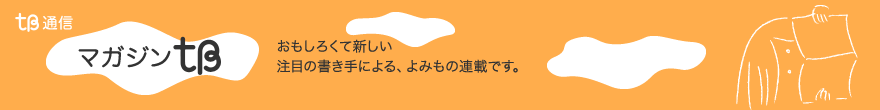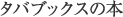翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
(2024/7/26)
前編はこちらです
***
一緒に訳者としてインタビューを受けていたあるとき、彼女が少し感極まったことがあった。自身の妊娠を告げた時、私が即座に口にした「おめでとう」の言葉が、うれしかったと言う。隣にいた私には、彼女が少し涙ぐんでいるようにも見えた。
誰かがとっさに発した「おめでとう」を稀有なものに受け止めるくらい、いろんな人にいろんなことを言われたのだろうか。彼女の状況を想うと胸が痛んだが、それ以上に私は、彼女が語る「小山内さん」に当惑していた。その場では照れ隠しのような笑いを浮かべていたけれど、正直おかしいなあ、と思っていた。私は人の妊娠を素直に喜べるような、そんな人間じゃなかったはずなのに。
80年代に10代を過ごした私は、「女性はいずれ妻になり、母になる」というコースを、当然のものと受け止めて成長した。今から考えるとどれだけ情報過疎なのだろうと思うが、全く疑問を抱かなかった。
自分の周りの昭和生まれの女子も、大体がそんな感じだった。恋人ができれば結婚をせっつく。「相手が煮えきらない」というのは、結婚に明確な態度を示さないときのよくある台詞だ。プロポーズを言わせたら勝利。そう、勝ち負けだった。恐ろしい。そうやって結婚した友人たちがこの10数年で立て続けに離婚しているから、やはりあのノリは間違っていたのだろう。そもそも、結婚といえば法律婚、入籍といえば異性の男性の苗字になるのが、当時私が属していた世界での「普通」だった。
結婚がそんな調子だから、妊娠・出産も既定路線だった。なのに、諸般の事情で自分には妊娠が限りなく困難だとわかったとき、比喩でなく目の前が真っ暗になった。それでも「完全に困難」というのであればまだラクだったろうと思う。現代医療にしがみつけば、自分以外の人間の協力も得られれば、なんとか叶えられそうな低い低い成功確率があることに余計苦しんだ。諦められればいいのに、諦め方がわからないのだ。「諦めるな」とはずいぶん言われてきたが、諦め方はただの一度も教わったことがなかった。
周りの態度にも心が乱れた。母親に「自分の子どもを抱けないなんて可哀想」と言われ、本人に悪気がないのは十分わかるものの、どう返事をしていいかわからなかった。可哀想なのか。自分の子どもを抱けない女は可哀想なのか。「出産して初めて一人前になった気がする」という、今思えば、まあそれも偽らざる気持ちなのだろうという芸能人のインタビューにも傷ついたし、夫婦で出かけた旅館の番頭さんに「子どもがいないなんてよくありませんねえ」と言われて抗議文を送らずにはいられなかった。毎年大量に届く、友人知人親戚からの子どもの写真入り年賀状は、5秒以上は見ないようにした。見続けると、産んでない子の歳を数えることになる。
そんな、すりこみの既定路線と戦っていた頃に出会ったのがハングルだった。辞書の引き方もわからない語学を、30代半ばで始めるのは結構なエネルギーが要る。だからこそ夢中になったし、検定試験を1つクリアするごとに自分にも何かできるという自信につながった。何より、別な人生を知った。隣国。違う文化。そこにいるさまざまな人々。さまざまな人生。
彼女と出会った時、すでに私は40を過ぎていたから、「子どもを持つこと」への期待も挫折もある程度薄まっていた。それよりも、覚えたハングルを使いこなすほうに頭がいっていた。だからだろうか。彼女から妊娠を告げられた時、まっさきに思ったのは「めでたい!」だった。そして次に考えたのは、妊娠出産でこの人が仕事上悔しい思いをしないよう、私は何をしようか、だった。弟子を名乗って下訳をしようと本気で考えていた。
インタビューの場で、少し声を上ずらせて語る彼女の告白を聞いてようやく気が付いた。私は誰かの妊娠をおそらく初めて、心から、喜べていたのだ。親友にさえ、妊娠を告げられて「ああ、君もあっち側へいくのか」と思っていた私が。これは成長なのだろうか。それとも、私の真っ黒な心を凌駕するくらい、この人が善の人なのだろうか。
おそらくあの時、私は1つのトンネルを抜け出たのだろう。トンネルの出口で待っていたのは、何もかも違うのに確かに何かでつながれる、彼女だった。
ほぼ毎日、彼女とやりとりをしている。訳語の選択について。どうにも意味のとれない原文について。共訳作業のスケジュールについて。仕事に影響を及ぼしそうなプライベートの出来事について。面白い表現について。韓国と日本の酷い事件について。片手間でお腹に入れられる食べ物や飲み物について。本を簡単に持ち歩ける便利でおしゃれなグッズについて。誰かに放たれて以来、突き刺さったまま抜けない毒矢のような言葉について。語ると、別な角度からの彼女の読みが返ってくる。それは自分の心模様を人に翻訳してもらっているのに近い。ああ、そうなんだ。なるほどな。どこかで自分が客観視できる。これこそが、翻訳者を友人に持つことの醍醐味かもしれない。
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子