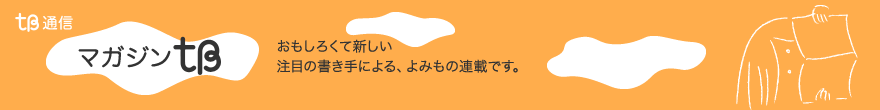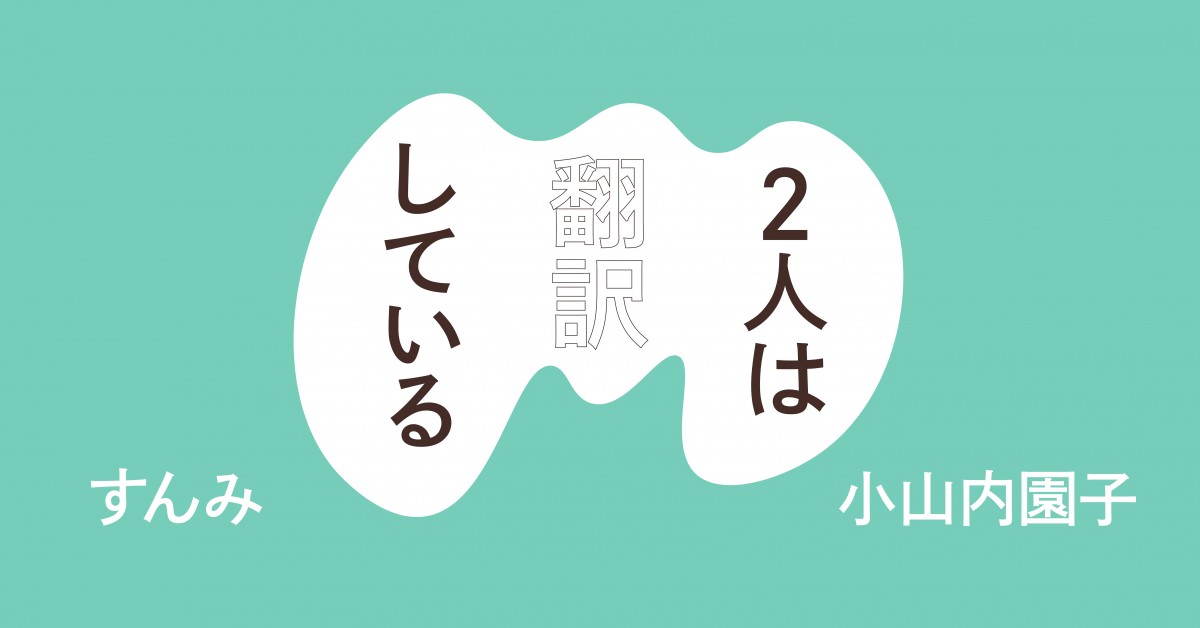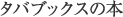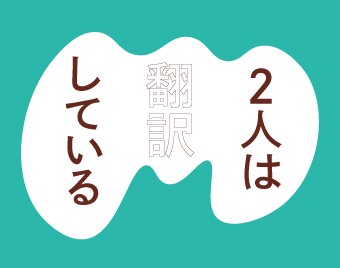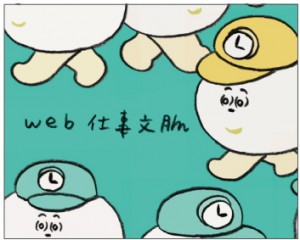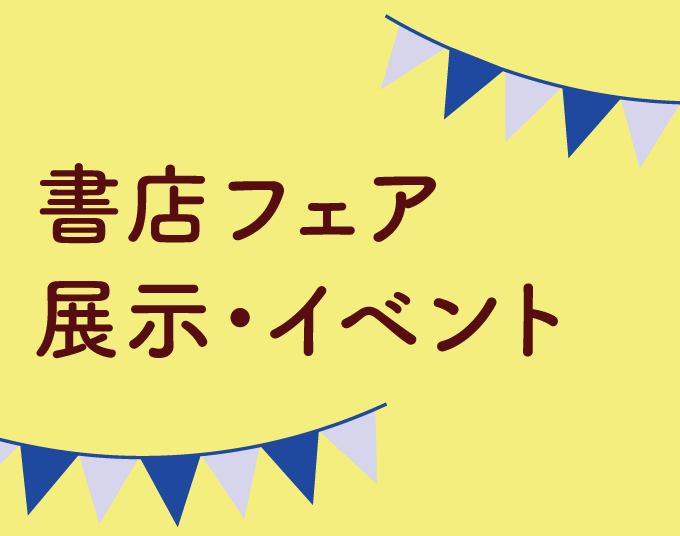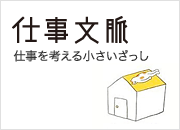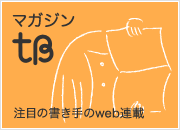翻訳ができる体(前編)/小山内園子
(2025/6/26)
翻訳作業は基本、座ってばかりである。
「座業」という言葉があるけれど、まさにそれ。デスクトップのパソコンにキーボード、紙の束、辞書、辞書アプリが入っているiPad、「いちばん使いやすい色鉛筆」と愛用している水性のダーマトグラフ、「いちばん使い勝手がいい」と愛用している韓国のダイソーのフィルム付箋、コーヒー、キャンディの瓶、用途ごとに使い分ける眼鏡などなどに囲まれて、一度イスに腰を下ろせばあとは目と腕以外、ほとんど動かさない。
「紙の束」というのは原書のコピーで、自分の最も見やすいサイズに151%拡大したものだ。それをモニター脇において見ながら、訳文を打ち込んでいく。最初の稿は訳の抜けを防ぐために、1段落終わったところで訳文のできている行を1行ずつ、ダーマトグラフ(作品のイメージに合わせて色を選ぶ。今は毒々しい話を訳しているので紫)で紙にチェックを入れていく。……なんというか、手作業である。「手仕事ニッポン」という風情が漂っている。
興に乗れば何時間も作業に没頭してトイレに行く時間も惜しくなるほどだが、この興に乗るまでが実はえらく長い。机に向かっても、最初のうちはたいていぐずぐずしている。
パソコンの電源を入れて、まずはメールのチェック。おそらく設定がまずいのだろう、受信トレイには毎日、不届きな輩(やから)からの謎のメールばかりが並んでいる。いっぽう、仕事相手からの重要な案件は、なぜか迷惑メールのフォルダに振り分けられている。大事なメールを受信トレイへ救出し、受信トレイの不届き者を迷惑メールへ追放・削除しているうちに、うっかり大事なメールのほうを消してしまって、ぴえんとなったりもする。
ようやくメールの整理が終わっても、すぐには翻訳作業に入らない。なぜか必ず、Yahoo!のトップ画面に飛んでしまう。そして芸能ニュースなどをぼんやりと読み、〈そうか、あの俳優、江南(カンナム)にビル持ってたのか〉などとひとり感慨にふけり、さらに続けて、どうでもいいことを検索し始める。たとえば今日の場合、前の晩に友人と電話していた時に2人とも名前が思い出せなかった、子泣きじじいに似た妖精の正式名称とか、やはり話に出てきたドラマの原作本の中古底値とか、電話の最中に窓から入ってきた、黒くて、ウエストがくびれてて、小型のハチか大型のアリのようなあれは何の虫だろう、などということを検索した。……いずれも、まったく急を要さない案件である。なんなら一生知らなくても構わない。でも、調べてしまう。たぶん調べたいのではなくて、仕事をしたくないのだろう。
それでも、あるタイミングまでくると、このぐだぐだにも底つき感が生まれる。「じゃ、やりますか」などと自分に声をかけて、ようやく翻訳中の原稿を画面に広げる。ここまでで、だいたい40分は軽く過ぎている。自分の仕事部屋をコックピットと例える人がいるが、私の場合は軟禁部屋に近い。足を踏み入れれば広がるであろう別の世界に、すぐには入れない。必ず道草してしまう。そして、一度入ると今度はなかなかそこから出られなくなる。
別の世界では、作品の登場人物たちがいきいきと動いている。訳者の私は、キャラクターを追いかけながらその声に耳をすまし、文脈の中で動詞、助詞、副詞、語尾などさまざまな選択をする。何度も読んでいるはずなのにまた先が知りたくなって、3ページ、4ページ、5ページと訳が進んでいく。そうしていて突然、「はて?」と思うような箇所に出くわす。原文の意味がとれないとか、ぴったりの訳語がありそうなのに浮かばないとか、旅の途中に巨大な岩石がごろんと転がり落ちてきて、道が塞がれてしまうようなイメージである。でも、進まなくてはいけない。よじのぼったり、迂回したり、とにかく、さまざまな試行錯誤の末どうにか翻訳ロードに戻って、また終着点を目指す。物語の世界をアドベンチャーする気分は、探検家に近いのかもしれない。
とはいえ、実際の私は探検どころか1歩も歩いていない。歩いていないだけでなく、脳が疲れるのか、やたらキャンディばかり食べている。今では自分に「キャンディ禁止令」を課したのでかなり抑えられるようになったが、初めての訳書が出た時は、運動不足にキャンディの食い過ぎが重なって5キロ太り、虚血性腸炎で入院までした。
翻訳業をするようになって、まもなく10年になる。座りっぱなしの時間は結構なものだ。年も年だし、さすがにこれはマズイんじゃないだろうか? 少しは体を動かしたほうがいいのでは? 気になり始めたのは1年ほど前のことだった。
座業といえば作家だろう。翻訳とはくらべものにならないくらい、産みの苦しみの大きい創作活動。自分で結末にたどりつかなければならないのが何より大変だと思う。翻訳者の私が「今日はここまでにしよう」と1日のノルマを決められるのは、ひとえに結末が決まっているから。作家の場合はゼロから、無から有を作り出すのだ。すごい。気が付けば座りっぱなしだったということなど、数限りなくあるに違いない。
運動不足マズイマズイ、となった時、思いついたのは、やりとりのある韓国の作家にノウハウを訊くことだった。物語を作り出す作家は作品に没頭するプロでもあり、座業のベテランでもある。ここはひとつ、先人の教えに耳を傾けよう!……だが、「作家様、運動不足はどうしてますか?」などといきなりメールを送りつけるわけにもいかないので、何かの折にさりげなく訊いてみることにした。
タイミングは思った以上に早く訪れた。とある作品の翻訳中、私がギックリ腰もどきになったのだ。ちょうど作品の疑問点についてメールを送る予定だったから、質問項目と合わせて「最近腰をいためてしまって、椅子に座っているのがつらい(のでご連絡するのが遅くなってすいませんㅠㅠ)」という、近況報告とも言い訳ともつかないことを書き添えてみた。すると先方から、「翻訳家も小説家も運動不足になりがちですよね!」と触れてくるではないか。いまだ! このチャンス、逃すまじ!! 私は思いきって訊いてみた。作家様は、運動不足の対策はしてますか? 何かいい方法があれば、ぜひ教えてください♪
「部屋にエアロバイクを置いています。あまり外に出ない生活なので、思い立った時にすぐできるように。しょっちゅうではないですが、意識的に乗るようにしています」
エ、エアロバイクぅ?! 部屋にぃ? 読みながら声が出た。彼女のメールはさらに続いていた。
「小説を書ける体でいるために、努力しなければならないじゃないですか。小山内さんの場合は、翻訳ができる体ですよね」
* * *
後編に続きます。
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子