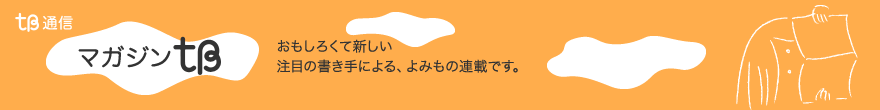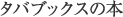参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
(2024/9/26)
小説を翻訳していると、作品への自分のアプローチの仕方は、マンガ『ガラスの仮面』を徹底的になぞっていると気づかされる。ご存じだろうか、美内すずえ作『ガラスの仮面』を。連載開始はなんと1975年で、現在54歳の私がまだ幼稚園年長組だった頃。スタートしてからまもなく半世紀が経つというのに、2024年9月現在未完の伝説の少女漫画だ。友人の中でも最高齢の75歳は「死ぬ前にどうしても最終回が読みたい」と何度か本気で口にしている。
主人公は、地味で何の取り柄もない少女と言われながら、演技に対しては並々ならぬ情熱と才能を抱いている北島マヤ。かつて師が演じた演劇界の不朽の名作「紅天女(くれないてんにょ)」の主役を演じることを目標に、さまざまな不幸にもめげず、演技の道を究めていく。この「紅天女」役をめぐって火花を散らすライバルが、映画監督と大女優のあいだに生まれ、「演劇界のサラブレット」「美貌の天才少女」の名をほしいままにしてきた姫川亜弓である。2人を軸にして進むストーリーは、マヤと亜弓が立つ舞台の演目が、劇中劇のかたちで描かれていく。
このマヤと亜弓の役作りのプロセスが、とにかく凄まじい。
たとえば、まだ演技を習い始めたばかりのマヤは、いきなり『若草物語』のベス役に抜擢される。だが、自分とは生まれも育ちも違う「ベス」という少女がいまひとつ理解できず、とりあえずシナリオに書かれている通りの動作をして、演出家に激しく叱責される。
「いったいベスがどういう気持ちで○○したかわかっているのか!」
「きみの演技にはまるで裏付けができてないんだ!」
「まず気持ちがあって、その気持ちが動作やセリフを言わせるんだ!」
それでもマヤにはベスがつかめない。このままでは役をおろされるという事態になったとき、師の月影千草は、マヤに特別訓練を命じる。それは、ベスの衣装を着て「1週間ベスとして生きる」こと。マヤはその1週間、真面目にベスとして暮らす。シナリオなど手放してベスと同じように編み物をし、仔猫を飼い、家事をしていくうちにどんどん想像が広がって、家の中で家族を想う病弱なベスの感情を獲得できてしまう。無事役にとどまったマヤは、本番で40度の高熱を出しながら、舞台袖で月影千草にしっかりしろとバケツの水を浴びせかけられながら、ほぼ憑依に近い状態で猩紅熱にかかったベスを熱演する。周囲はマヤを「気味の悪い子」「恐ろしい子」「ただものじゃない」と感じる。
他方、キャリアもスキルも十分ある亜弓のネックになるのは、その恵まれすぎた容姿と環境だ。なにせ住んでいるのは豪邸、身の回りの世話をするのは「ばあや」である。妬まれることはあっても、マヤの登場以前は誰かに嫉妬を感じることなど皆無の人生だった。だからこそ未経験なことも多い。その不足を、さまざまなアプローチで補うのだ。恋心に身を焼く役の時は、わざと男にモーションをかけて、彼が自分にうっとりするまなざしを演技の参考にする。もちろん役が終れば男のことはポイ捨てだ。実父の王の裏切りで母を失い、自らも幽閉され、ひたすら恨みをつのらせる不遇の王女の役についた時は、わざわざ特殊メイクで顔に傷をこさえて、危険な街へ夜ごと繰り出し、憎悪の感覚を体得する。
マヤも亜弓も、演技の前提にあるのは、その役の感情を身体に叩き込むことだ。感情の裏付けがなければ舞台の上での動きは上っ面になり、セリフに説得力が生まれないと考えている。そしてその部分が、私には文学作品の翻訳の手本に見えてしまうのである。
***
小説の翻訳をする。その時、ただ頭で選んだ語彙では平板に感じられることがある。辞書的な意味では正しくても、場面として、物語の話者や登場人物の言葉選びのベクトルとして、どこか落ち着かない。想像力が足りていない、頭に絵が描けていないと感じる。そんな時こそ『ガラスの仮面』の出番である。マヤと亜弓にならって、もう一度作品の中に入り込み、登場人物に憑依を試みる。
チョ・ナムジュの短編『彼女の名前は』を担当した時のこと。この本はすんみさんと共訳で、解説はソウル在住のライター、成川彩さんが書いてくださった。刊行前に成川さんが来日するタイミングで、編集者さんと4人で打ち合わせをし、そこである収録作品の話になった。貧しくて生理用ナプキンを買えない高校生の物語「公転周期」だ。
手持ちのナプキンをきらしてしまった主人公は、制服が経血で汚れるかもしれないからと、生理中は学校を欠席する。家では古くなったTシャツを小さく切ってナプキン替わりに使っている。だが、半地下よりさらに下の地下1階にある家のため、Tシャツナプキンは洗っても生乾きになりやすく、男きょうだいの目も気になる。そこで彼女は、生理中「昼間はだいたい、洗面所の排水溝のところにしゃがんで」過ごす。「足がしびれたりとか、お腹が痛くなったりしたら、Tシャツナプキンあてて、ちょっと寝っ転がるとかして」いる。
最初に原文を読んで、〈排水溝にしゃがむ!?〉と目が点になった。その作品は私の担当だったが、そういう時の身体的感覚はゼロだった。そこで自分もやってみた。真冬に、下半身だけ裸で、風呂場の排水溝で。
排水溝をまたぐ形でしゃがむ。すると、あっというまに足がしびれてくる。ああ、これは和式トイレに長時間しゃがんでいるようなものか、とわかる。和式トイレは数分だから耐えられるのであって、日がな1日しゃがんでいたらそりゃしんどい。小説の中の彼女も、ときどき風呂場の床にお尻をつけて休憩したんだろうと考える。だが、やってみると床が経血で汚れる。洗い流せば足場が濡れて、それでなくても寒い冬の風呂場が、よけい耐えがたいものになる。これはなかなか大変な行動だ。生理のために学校を休んだ彼女は、こんなことをしていたのか。しゃがみながら何を考えただろう。みんな今頃何やってるかな。授業どこまで進んだかな。時間の進みがひどく遅く感じられたはずだ。
「5分やっただけで冷えきっちゃったんですよ。あと、ポーズが難しいんですよね」
実験した感想を何の気なしに披瀝している途中で、他のみんなが引いているのに気が付いた。確か、すんみさんだったと思う。「それ本当に、やったんですか?」と、いつもより半音高い声で訊かれた。
***
後編に続きます
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子