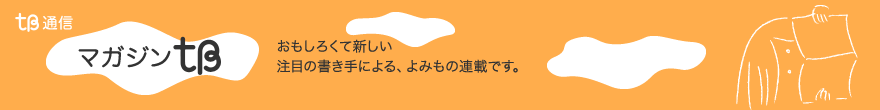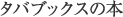翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
(2024/7/25)
韓国を代表するエッセイスト2人が、昨年共著でエッセイ集を発表した。その中に互いのことを綴る章が置かれていて、読みながらうなった。友達を、なんて冷静に見ているんだ! 過剰な思い入れは一切感じられないながら、気がつけば「ここに描かれているこの人に会ってみたい」と思わせる文章だった。
そういえば、私にも1人いた。できれば淡々と、その魅力を綴ってみたい人。大好きだけれど不思議な人。友情よりもリスペクトのほうがまさり、その人が達成することを見届けたい人。私のことを別な視点から、翻訳してくれる人。
彼女との共訳作品の多くは、彼女が引き寄せた仕事だ。こんな本がある。こういうところが出色。こんな読者なら読んでくれると思う。軽くお茶をするはずが仕事の話になって、具体的な書名がぽんぽん彼女の口から飛び出す。今ではだいぶ慣れたが、会うのが3回目くらいでいきなり共訳の話を持ち出されたときは内心とまどった。と同時に、「何を夢みたいなことを……フフフ」と少し半笑いになった。
実際、当時は夢みたいなことだったのだ。そもそも私は、翻訳者を名乗ってはいても訳した書籍は一冊のみ。その後の予定は白紙に近い開店休業状態だった。自分の実力不足もさることながら、韓国の書籍をめぐる状況も、2018年初頭と今ではまるで違っていた。韓国文学の棚があるのは、大型書店かアジア文学に特化した専門書店ぐらいのものだったし、「この作品は面白い、日本に紹介したい」と韓国の本の出版を企画書にまとめて出版社に送っても、たいがいがナシのつぶてか、あるいは「うちは既におつきあいのある翻訳者さんがおりますので」と門前払いを食らった。韓国書籍の出版自体が狭き門であり、そこを通過できる翻訳者の数も、また限られていた。
だから、フェミニズムのとても面白い本がある、共訳にできないかを担当の編集者さんに提案してみる、と彼女に言われたとき、前述のように半笑いが浮かんだ。改めて当時の手帳を確認してみると、突然その書名を持ち出されたのが2018年2月。共訳が認められ、翻訳作業が始まり、完成した訳稿を最初に送信したのが6月末。「何を夢みたいなことを……フフフ」は、夢では終わらなかった。
終わらなかったのだが、翻訳作業中も、彼女に対して「何を夢みたいなことを……汗」と思わせられることが何度かあった。最大の衝撃が走ったのは訳稿を出版社に送った後だった。すっかり翻訳は終わっているのに、やっぱり文体をすべて変更しよう、そのほうがこの本には適っている、と彼女に提案されたのだ。これまた手帳を見返すと、訳稿を提出した約3か月後の9月13日に「やり直しの日々、どよよ~ん(手書きのドクロ付き)」と書いてあり、そこから4日で、自分の担当パートの文体すべてを修正したことがわかる。「ことがわかる」とクールに書いてはいるが、ドクロを描いているあたり、心情的にはかなり荒れていたのだろう。
しかし、思えばあの時、私の脳は謎のアドレナリンの味を知ってしまったのだと思う。あきらかに楽しかった。そして、この人は私の何かをぶっ壊してくれる、と異常にワクワクした。
彼女より十数歳年上の私は、長く生きているぶん、思考回路にヘンな垢がどっぷりついていた。社会での人間関係や仕事の進め方で、まず最初に最悪のシナリオ想定してしまうという「危険予測癖」。空気を読み、その場でもっとも権力を握っている人間を嗅ぎ分けようとする「権力嗅覚」。周囲の意向に合わせて自分の信条をついつい曲げてしまう「自律型撤収モード」。それらの垢は、彼女と一緒に仕事をするようになってメリメリ落ちていった。まさに垢すり状態だった。
「〆切」への向き合い方が端的な例だ。もともと小心者で、人に嫌われたくない優等生的性格なのに加えて、社会人生活をスタートさせた場所が悪かった。テレビ局の新人ディレクターとして仕事を始め、父親くらいの年齢の男性上司数人に「どうせお前の作るものは大したことないんだから、とにかく納期だけ守れ」と呪いをかけられているうちに、「とにかく納期だけは守るよい子病」が持病になっていた。
だから、とにもかくにも翻訳が終わって次のステップへ進みつつある原稿に「いや、やっぱり文体変えましょう」と待ったをかけられる彼女は、私にとって、ほとんど違う星から来た人だった。年齢とか国籍とか母語とか違う点はいろいろあるが、そういう想定の範囲の違いではなくて、何か別の星から、大事なメッセージを携えてやってきた人のように見えた。
もちろん、最初の〆切までに、「これだ!」と思う文体が見つかればそれにこしたことはない。だが逆を言えば、締め切りまでは必死に文体を考えたとしても、納品してしまえばそれで終了、考えることにピリオドを打つパターンのほうが、私を含め圧倒的多数派だと思う。
彼女は違う。編集者さんに渡した原稿に実はうっすら残っている、もやもやや引っ掛かり。そこから目を逸らさず、〆切のあとも考え続けていたのだ。そもそも〆切前だって、彼女はずっと試行錯誤していた。連日のように進捗状況を報告し合っていたから、そのことは私が一番よくわかっている。つまり、彼女が何か思いつくときは必然なのだ。それだけの時間を必死に作業して、考え抜いて、試した末に木から熟した実が落ちるように、降ってくるアイデア。もっといいものになりそうな予感があるときに、「え~いまさらですか?」というリアクションを恐れずに、口を開く勇気。
「そっちのほうが面白そうですね」と反応してくれる編集者さんがいて、本はまさに結実した。私は彼女について行こうと決めた。もっと粘ったら、いい翻訳、いい作品になりそうだという予感を、納期より優先できるようになった。もちろん締め切りを守る気は十分なのだが。
***
後編に続きます
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子