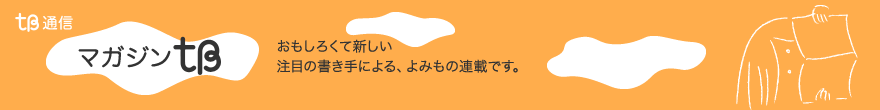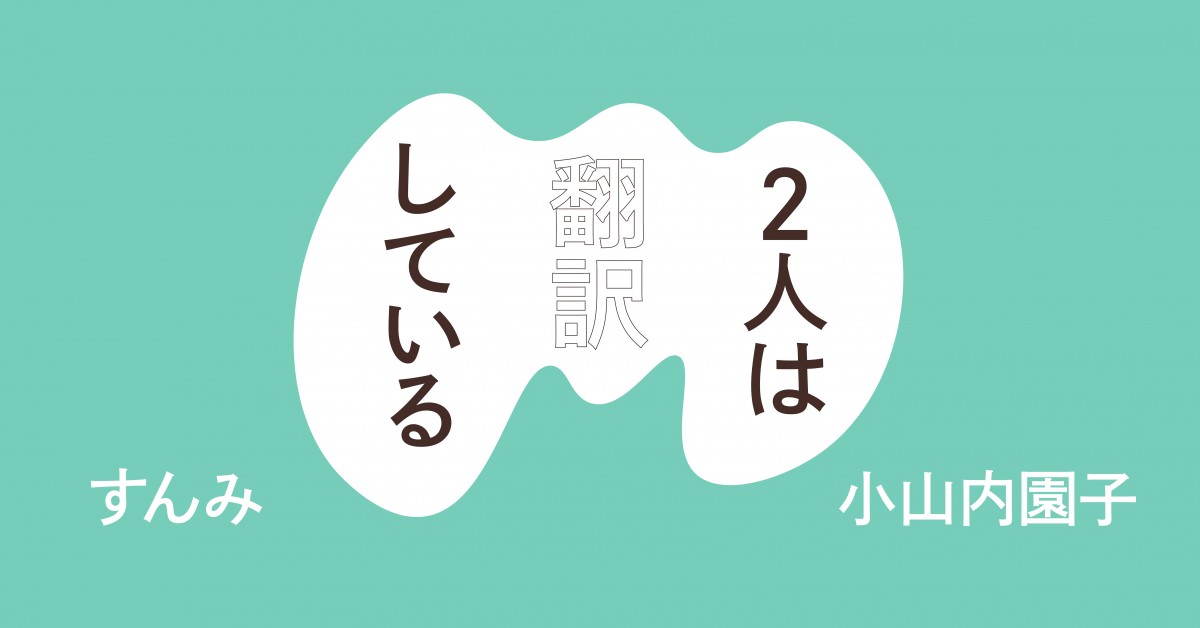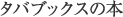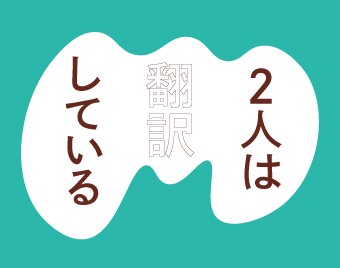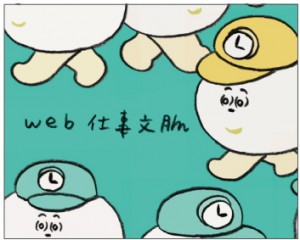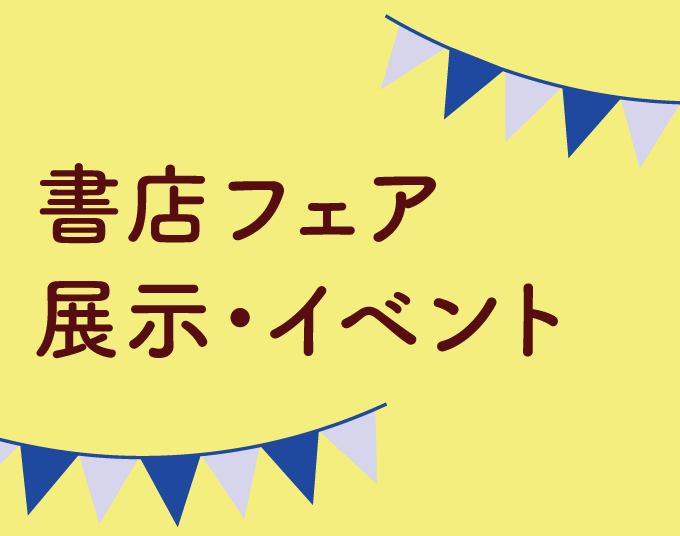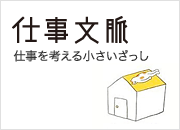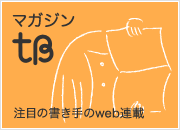ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
(2025/8/21)
厚手のバスタオルでも3秒あれば乾いてしまいそうな、放置し続ければカリカリに焼けて、鶏皮レベルにまでなってしまいそうな、異常に強い日差しが頭頂部に突き刺さる。ただ洗濯物を干すだけなのに、ひさしのないベランダでは帽子が欠かせない。昨夜も気象予報士が、ニュースで口を極めて言っていた。関東は40℃越えになる、死の危険がある、命を守って行動してほしい。
一刻も早く洗濯物を干し終えて部屋に戻ろうと手を動かしていると、「〇〇さーん、〇〇さーん」と、地上でうちの苗字が聞こえる。法律婚をする時、不覚にもジャンケンに負けて、私は配偶者の苗字になった。もう何十年も、近所では「〇〇さん」と呼ばれているのだが、相変わらずすぐには反応できない。〈あ、夫の名前が呼ばれてる〉と思って見下ろすと、3軒先に住むNさんが戸惑ったような顔をして立っていた。「蛇が家に居座っちゃってて……。」
70代後半のNさんは何年か前に夫に先立たれ、今は一軒家に1人暮らしだ。夫の介護のために看護師の職を退き、趣味の旅行も諦め、外出といえば、食料の買い出しと夫の通院の付き添いぐらいのものだったのが、ある日突然夫が急逝。以来、人生初の一人暮らしを続けている。
同じ北の出身だったこともあり、コロナ禍前はよく招かれて「お茶のみ」をしていた。コーヒーとクッキーとかの組み合わせではなくて、私たちの故郷のおばちゃんたちがしているような、漬物をぽりぽり齧りつつ日本茶を飲むティータイムだ。漬物の野菜は自家製。漬物だけではない。家の中には、至る所にNさんの手が感じられた。掃き清められた三和土。庭から手折った花が飾られている下駄箱——。
蛇は、その下駄箱の下にもぐりこんでいるという。
「ドアを開けたらね、蛇がね、スッって入ってね、ずっと見張ってたの」
「私、生き物の中で蛇が一番嫌いなのよ」
気象予報士の話は本当だった。炎天下に出ただけでクラクラする。なのにNさんは、長袖に長ズボン、長靴、帽子という庭仕事スタイルでいながら、まったく暑がっていない。そっと腕を抱いて、もじもじしている。状況を尋ねても今一つ要領を得ない。蛇が入ったのは何時頃なんだろう。それに、見張る? 何のために? 疑問で頭がいっぱいになるが、悟られないようにわざとあっけらかんとした声を作って、また訊く。
「へえ~。どれくらいの大きさの蛇なんですか?」
「あたしの、人差し指くらい?」
ちっちゃ。カナヘビでは? しかしよく聞くと、それは長さではなく太さのことらしかった。ああ、体長どれくらいですか、って質問するべきだったか。でもこの年代に「タイチョウ」というと、即座に血圧とか体温とかの話が浮かぶかもしれないし。漢字語は難しいな。
そんなことを思いながら、持ってきた携帯電話で「家に蛇が入り込んだ時の対処法」を検索する。毒蛇でないかぎり人に悪さはしない、とあった。出口を用意してそっとしておけば、自分から帰っていくとも。検索結果をNさんに伝え、とりあえず一度、私が今の蛇の様子を確認してみることになった。Nさんには離れていてもらって、玄関の奥へ足を進める。
相変わらず、掃除の行き届いた玄関だった。ホウキを借りて、下駄箱の下にそっとさし入れる。それらしきものはいない。下駄箱脇の傘立ての裏も探ってみるが、やっぱりいない。いないと伝えると、「ずっと見張ってたのに。いたのに。ずっといたの」と、Nさんは何か、蛇にいてほしかったような口ぶりになる。
「ほら、私のことを呼びに来た時、Nさん、玄関を離れてましたよね? あの時にきっと出て行ったんですよ? 見張りがいなくなった隙に、蛇も『今だー!!』って感じで脱出したんでは?」
ああ、そっかー。また見かけたら、〇〇さんお願いね。Nさんの表情が少しやわらいだ。いつもいだのか、庭のキュウリを2本、お土産にくれた。
家へ戻りながら「見えない蛇」と口に出してみる。数日前の友人の話を思い出す。友人の母親も、現在「人生初」の1人暮らし中だ。そしてやはり、家にいろんな存在が訪ねて来ているらしい。実家が遠くてなかなか帰省ができないからと、母親が1人暮らしになってから、友人はちょくちょく実家に電話を入れていた。初めのうち母親は、お菓子作りをしたり習い事をしたりと、自分だけの自由な時間を謳歌している様子だった。そのうち「1人分作るのは億劫だから」と三度の食事も冷凍食品やインスタント食品で済ませるようになり、最近ではいろいろな人が実家に「遊びに」来るようになった。女子高時代の同級生、結婚前に勤めていた職場の先輩。出産の時、産院で同じ部屋だった人……。それが本当なら数十年来のつきあいのはずだが、娘である友人にとっては、いずれも初めましての名前ばかり。母親と同世代なら年齢は80を越えているだろうし、高齢者の移動手段が少ない地方で、どうやって来ているのかもはっきりしない。そもそも、彼女の実家は2年前に引っ越していた。引っ越しのお知らせハガキを作ろうかと母親に訊いたとき、「そういうのは面倒だから」と一蹴された記憶もある。では、来訪者たちはどうやって住所を知ったのか?
「見えない友達がいるのよ、うちの母親。でもね、それが本当の話かどうか、追及するのも怖いんだよね」
キュウリ2本を握り締めながら、「そうだよな」と思う。追及してしまって、事実が全く違っていたら。自分も気まずいし、相手を追い込むことになりかねない。
だが、私がNさんに話にあっけらかんを装ったのは、必ずしもそういう理由だけではなかった。私の場合、客観的事実ではなくその人が信じる話、ささやかで、生きるよすがとなっているような話に心惹かれるのだ。もっといえば、そういう話を聞いた日は、なぜだか妙に翻訳作業がはかどるのだ。
***
後編に続きます
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子