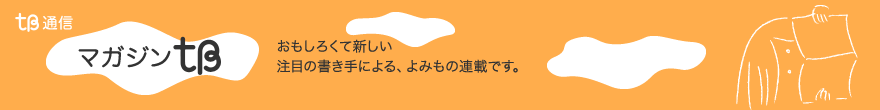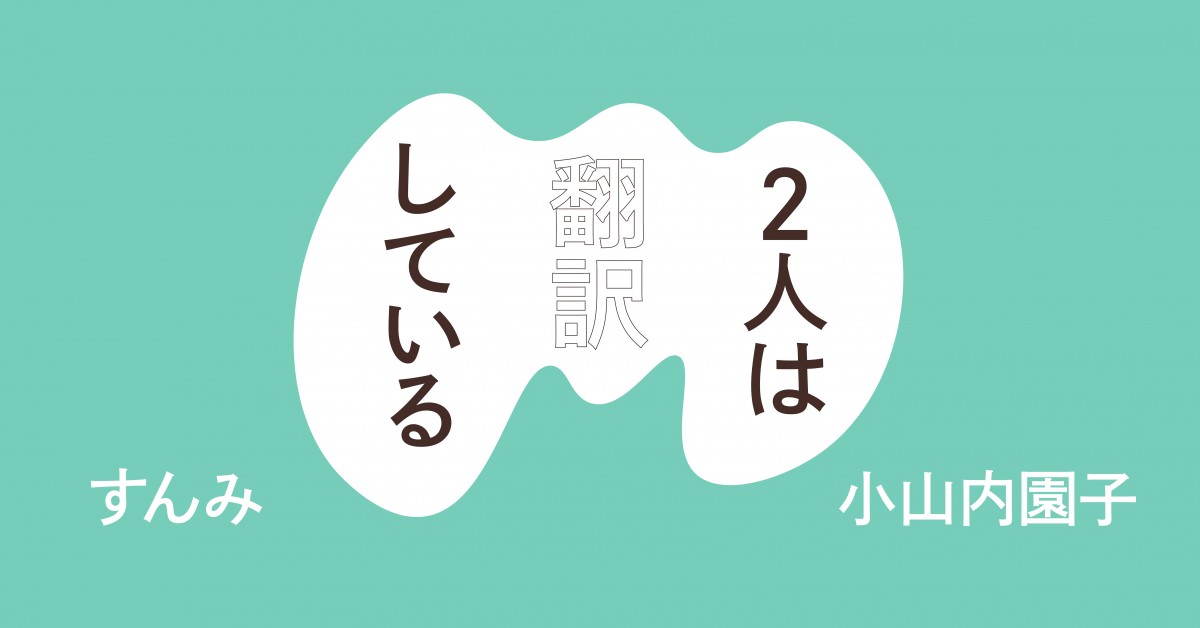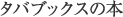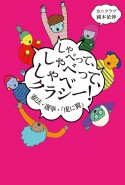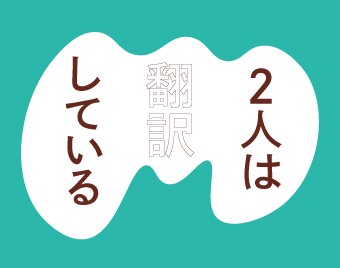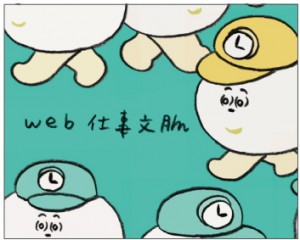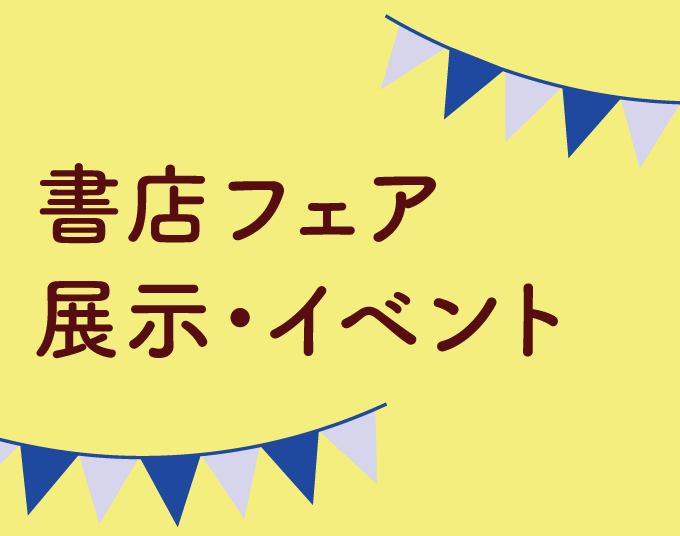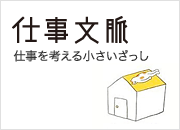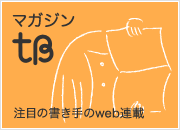世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
(2025/7/30)
前編はこちらです
*
キム・グミ『あまりにも真昼の恋愛』が含まれた「韓国文学のオクリモノシリーズ」は、斎藤真理子さん訳のハン・ガン『ギリシャ語の時間』をはじめ、魅力的な作品群とそのデザインが評判となった。そして同じ年に刊行されたイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ』が、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』というクエスチョンに対するアンサーということで話題に挙がった。ありがたいことに、そのおかげで韓国文学の翻訳者として認知されるようになり、いまも仕事を続けられている。
運よく、様々な分野の作品に関わることができた。純文学からエンタメ性の高い文学、YA小説、絵本、エッセイ、人文書など。これも韓国文学への関心が高まっていた時期に、仕事を始めたおかげだろう。短い期間に、いろいろな経験ができたのは幸運に違いない。だが一方で、専門分野を作るべきではないかという不安もあった。立ち位置の定まらない翻訳者になっているのでは? と悩むこともある。
しかし、自分で選んだことだった。私は、翻訳者として特定のアイデンティティを確立するより、様々な作品、言葉、メッセージが自分を通り過ぎていく、ある種の「交差点」でありたいと願った。だからこそ、ジャンルを問わず、一つ一つの作品に真摯に向き合ってきた。
2022年には、韓国の出版社イッタが行った詩の翻訳プロジェクトに参加した。そのことがきっかけで、ルポ作家ウンユさんのインタビューを受けることになった。解放村(ヘバンチョン)【註:ソウル市龍山区にある地域。正式な地名ではなく、日本の植民地支配からの解放後、海外からの帰国した人々などが暮らすようになったことからこのような名前が定着した】にある独立書店「コヨソサ(goyo bookshop)」で、翻訳者として「交差点」でありたいという思いを打ち明けたところ、ウンユさんは次のような素敵な言葉で私を説明してくれた。
すんみの歴史は他人の歴史だ。(中略)そうやって彼女が捉えた他の人々の輝く瞬間は、星座のように繋がり、彼女の人生を導いた。
自分がこれまでたどってきた道をこのように表現してもらえたことが嬉しかった。そして、他の人々の輝く瞬間が、私を導いてくれたように、私の作業が他の誰かの暗闇を照らしてほしいと心から願った。そのためには、自分が誰かの輝きを受け止められる「器」にならなければならないと思う。古井由吉の作品に出てくる登場人物が、部屋にじっとしていながら外から聞こえてくる言葉に耳を傾けているように、作品から聞こえてくる様々な音に耳をすませられる集中力と揺れ続けるための体力が必要だと感じた。当時インタビューで語ったその思いは、いまでも変わらない。
古井由吉の小説の登場人物たちは「空っぽ」です。その代わり、外部からいろいろなものが入ってきます。本の文章が入ってきて、他人の言葉が入ってくる。そのように生きてみるのもいいのではないか、揺られながら生きている今も悪くないように感じます。
私はこれまで出会ってきた人たち、かかわってきた作品に影響されてきた。そして、少しずつ自分を変化させ、どこにも固定されずにしなやかに揺られながら流れに身を任せてきた。そのおかげで、自分では考えたこともない世界に出会うことができた気がする。
例えば、フェミニズム。文学を学ぶ間、どうしても男性作家が書いた小説と男性評論家が書いた評論を読む機会が多く、フェミニズムなど別の角度から作品を考えたことがあまりなかった。しかし、タバブックスから『私たちにはことばが必要だ』を翻訳出版したいという依頼が来た時、この先、物事の見方が大きく変わるような予感がした。小山内さんと電話で共訳の相談をしながら、高揚した声で「小山内さん、大変なことになると思います!」と言ったことを今でも鮮明に覚えている。
『私たちにはことばが必要だ』を始め、チョ・ナムジュやチョン・セランなどによるフェミニズム小説や、50代以上の女性たちの労働にスポットライトを当てた『私たちに名刺がないだけで仕事してこなかったわけじゃない』(大和書房、尹怡景との共訳)など、女性の人生や労働を取り上げた作品群は、それまで知らなかった世界へ踏み出すための、新しい地図を私の手に握らせてくれた。
チェ・ジニョン『ディア・マイ・シスター』では、子どもの頃に信じていた大人に性暴力を受けた主人公のジェヤが、じっくり時間をかけて自らの言葉を鋭く磨き上げ、止まったような時間を突き破って前に進もうとする姿が描かれる。ジェヤが事件後に磨き上げた考えと言葉は、八方ふさがりの現実を斬り拓くための一振りの刃になったのだ。
私が訳した作品も、誰かにとって現実を破り、新しい地図を作り上げるための武器になってほしい。韓国でジョゼ・サラマーゴ『白の闇』など数多くの作品を手掛けた翻訳者チョン・ヨンモクは、翻訳についての考えをまとめたエッセイ『完全なる翻訳から完全なる言葉へ』(未邦訳)でこのように綴っている。
海外の文化や社会の新しい言葉と概念を翻訳することは、単にそれにぴったりと当てはまる韓国語を見つける作業ではない、と理解しなければならない。私たちの現実や歴史に、あるいはまだ私たちの思考の中にないものを作り上げることもよくあるのだ。
韓国文学、そして私が訳した作品が、読者が自身の思考の中にない「外」を経験し、新しい地図を作るための道具になればと思う。私の翻訳がその助けになるならば、それ以上嬉しいことはないだろう。
すんみ
翻訳家。訳書にキム・グミ『敬愛の心』(晶文社)、チョン・セラン『八重歯が見たい』(亜紀書房)、ユン・ウンジュ他『女の子だから、男の子だからをなくす本』(エトセトラブックス)、ウン・ソホル他『5番レーン』(鈴木出版)、キム・サングン『星をつるよる』(パイ インターナショナル)、共訳書にチョ・ナムジュ『私たちが記したもの』(筑摩書房)、イ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(タバブックス)、ホンサムピギョル『未婚じゃなくて、非婚です』(左右社)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子