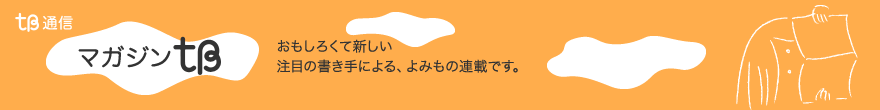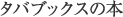一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
(2024/6/27)
小学生のあみ子は、お腹の中の子を亡くし、悲しみに耽っていた母親の回復を祝おうとして、弟のお墓をつくることにする。木の立て札に、習字がうまい友だちののり君に「一生のお願い」と頼んで「弟の墓」と字を書いてもらう。家に帰り、夕飯を準備している母親の手を引いて、例の立て札を立てておいた庭に出る。
「どこ行くの」
「こっちがわ、こっちがっわ」
(中略)
「きれいじゃろ」声をかけてみたが、振り返ろうともしない。「ねえきれいじゃろ」すごいね、きれいね、と言ってもらえると思ったのだ。「手作りよ。死体は入っとらんけどね」
母はあみ子に背を向けたままその場にしゃがみこみ、声を上げて泣きだした。最初、咳をしているのだと思った。高い音でコンコンと言っていたから。それが呻き声のようなものになったかと思うとすぐに確かな発声へと変化した。泣き声は大きく響き渡り、兄が玄関から飛びだしてきた。「どうしたん。お母さんどうしたん。あみ子」
「わからん。いきなり泣きだした」
「なんで、あっ。なにこれ」
母を喜ばせるつもりで、朝から立て札を抜き取り、習字の先生をしている母にいいものを母が喜ぶものを、という思いで習字がうまいのり君にお願いをして、せっせと動き回っていただろうあみ子。今村夏子『こちらあみ子』(ちくま文庫)を読んでいて、母がなぜ泣いているのかわからず、呆然としているあみ子の気持ちが痛いほどわかる気がした。
子どものころの私は、わからないことが多すぎたし、周りに馴染むこともできなかった。UFOを見つけると言って一人で草むらに隠れて夜遅くまで空を見張ったり、自分で捕ったカタツムリを小学校の前で販売したり、実験をすると言って公園の葉っぱを集めて火を放ったり。たいてい親や近所の人たちに見つかって大事に至らずに済んだけれど、いま思うと自分でも「あれは危なかったな」「あれは迷惑だったな」「あれはいけなかったな」という場面がいくつも頭に思い浮かぶ。
絵の習い事教室では、年上の男の子に馬乗りでボコボコにされたことがある。イーゼルを丸く並べて絵を描きながら、誰かが長く息を止められる人が勝ちの勝負をしようという提案をした。鼻を指でぎゅっとつまんだまま、負けず嫌いの私は「絶対負けないぞ」と声を出して言った。すると、年上の男の子は口で呼吸していると言って、私の負けを宣言した。しかし、私は口呼吸、鼻呼吸ということがうまく理解できず、自分の負けを認められなくて彼に食い掛った。それから口論になり、罵倒し合った末に、私は彼にボコボコにされてしまった。
小学生のころはこういう日の連続だった。言ってもいいことと言ってはいけないことの区別がつかず、兄から「何度も考えて話せ」と言われたこともあれば、六年生のときは理由もわからず担任の先生に毎日反省文を書かされ、卒業のときに反省文ノートが何冊もたまっていた。そうこうするうちに、うまく説明できないけれど自分は周りと何かズレている、という感覚を肌で感じるようになったと思う。
「わからない」という感覚には、ずいぶんと苦しめられた。自分の周りの状況がはっきりつかめないまま、焦点の合わないメガネをかけて暮らしているような日々だった。
そんな私がADHDだとわかったのは、出産後だった。もともと物忘れが激しく、計画的に、順序良く、物事を進めるのが苦手だったけれど、昔からちょっと変わっていたわけだし、ただだらしない性格なだけなんだろうと思っていた。
しかし、小さな子どもの命が自分の手にかかっていると思うと、「もともとそういう性格だから」と言い訳をしていられなくなった。毎日のルーチンはなんとかこなせたけれど、一歳健診や予防注射のように成長に合わせてちゃんと行わなければならないこと、スケジュールを確認し、病院を予約して、必要なものを持ち込まなければならないこと、などは私にとってあまりにもハードルが高すぎた。あれも忘れた、これも忘れた、と慌ててばかりいたある日のこと。保育園の入園申込みを忘れたことに気づき、もやもやとイライラが押さえられなくなった。自分の力だけではもはや改善策が見つからないのではないかと思った私は、ついに病院を訪れ、ADHDだという結果を得た。
なるほど、そういうことか。説明を聞きながらも納得した。特に、幼いころの自分の行動がものすごく腑に落ちた。いつももどかしさを感じながらも、「まともに」振る舞えない自分と初めて和解できた気がした。あんたもさ、誰にも気づいてもらえなくて大変だったんだろうね、と。
思えばこれまでも、そんな自分に折り合いをつけようとしてきたのだった。ADHDだと理解できる前、大学の頃くらいまで私は、いつの間にか「四次元(사차원)」(韓国では、どこか変わっている人という意味で使われている)キャラになっていて、どうにかみんなと同じになりたくて、行動や考えの「基準」となるものを探し求めていた。周りと変わらない行動が取れるようになりたかった。それで周りの子たちの行動を真似したりした。もし「正しい振る舞い方」「自然な受け答えの方法」という本があるなら読みたい、それか誰か教えてほしい、とずっと思っていた。そしてそんな自分に、「正解」を生きるのではなくて、「自分」を生きるということを教えてくれていたのは、いつも文学だった。
***
後編に続きます
すんみ
翻訳家。訳書にキム・グミ『敬愛の心』(晶文社)、チョン・セラン『八重歯が見たい』(亜紀書房)、ユン・ウンジュ他『女の子だから、男の子だからをなくす本』(エトセトラブックス)、ウン・ソホル他『5番レーン』(鈴木出版)、キム・サングン『星をつるよる』(パイ インターナショナル)、共訳書にチョ・ナムジュ『私たちが記したもの』(筑摩書房)、イ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(タバブックス)、ホンサムピギョル『未婚じゃなくて、非婚です』(左右社)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子