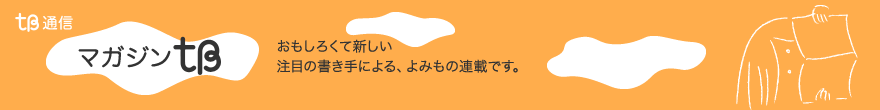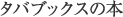「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
(2025/3/27)

この春は、少しすっきりした気分で迎えた。もう1つの職業である福祉の仕事で、自分の立ち位置が定まったからだ。これまで担当していた「ケアの必要な人をケアする」仕事から、「誰かをケアする人を、ケアする」仕事へ、舵を切ることにした。つまり、相談者と直接顔を合わせて、言葉を交わして支援をすることは減るという意味だ。そういう立場でソーシャルワークを続けると弥生三月に決意した。すっきりして、少し寂しい。
福祉の世界にも専門がある。私の場合は20年近く、女性相談一本で働いてきた。NPO法人に籍を置いて、出勤は週に2、3回。電話や面接で相談を受けるほか、長期で何人かの相談者を担当し、定期的に会って話を聞く。病院受診や弁護士との打ち合わせにも同行して、彼女たちが自分の意志を実現できるよう手伝う。
〈女性〉を切り口にした相談は、恋愛、結婚・離婚、DV、性暴力、児童虐待、セクハラ・パワハラ、賃金差別、生活困窮、年金問題、外国籍市民なら在留資格の問題と、それはもう本当に守備範囲が広い。似たような事例はあっても同じ事例は2つとない。そういった困りごとを抱えた相談者(ここが大事なところなのだが、世の中にはたまに、困っている人を「困った人」とザックリ決めつける輩がいる。そうじゃない。困っている人は「困りごとを抱えている人」だ。その点は声を大にして言いたい)の近くで、適切な距離感を保ちながらサポートするのが主たる業務だった。時には暗い秘密を共有しつつ、一緒に苦しい記憶に立ち向かう。家に帰っても誰かの人生が頭からなかなか離れない時、一種の息抜きになったのが韓国語学習だった。そして、ソーシャルワーカー歴が10数年になった時、翻訳がもう1つの仕事になった。
「人生経験は翻訳の肥し」とよく言われるが、このソーシャルワーク経験がなければ私は翻訳を続けていないだろうし、ひょっとしたらできなかっただろうとも思う。それだけ、出会った人それぞれの言葉遣い、仕草、姿勢、ものの考え方、一緒に向きあった社会の現実が、原書を読み解く時の参照例になった。具体的な想像は、より切実な訳語を選ぶ杖になる。
訳す作業だけではない。作品を選び、それを日本の出版社へアピールする時も、〈あの人たちの力になりそう〉〈あの問いへの答えになりそう〉と、読者層をイメージするきっかけをもたらしてくれた。たとえば、カン・ファギル著『別の人』という作品は、性被害を受けた女性達にこそ読んでほしいと出版社に紹介した作品だ。「同意なき性行為」を題材に、被害者の揺れる記憶と感情を丁寧に、レイヤーを重ねるようにして描いた、ミステリータッチの長編小説。被害者たちはそれぞれが大海に浮かぶ孤島のようで、経験を共有したり、誰かの経験から力を得たりすることができない。社会が加害には甘く、被害に酷なシステムであることが明らかにされる。だが、ラストは決して絶望では終わらない。
相談の場で出会った性暴力被害者との時間がなければ、おそらくこの原書とは出会えなかったはずだ。せめてもの恩返しにと、訳者あとがきには彼女たちへの謝辞を書き込んだ。
だが、翻訳の仕事が長くなるにつれて、だんだんに不安が頭をもたげてきた。
韓国文学が注目され、黒子のはずの訳者までイベントの参加や顔写真の掲載が増えてしまったからだ。たまたま相談者が私の顔写真に気づいたら、どんな気持ちになるだろうか。もし私なら、決していい気はしない、もっといえば不安になるだろうと思った。自分のことを、どこかでこいつ、しゃべってるんじゃないか? そう思われる気がした。
もちろん、そんなマネはしない。ソーシャルワーカーには職業上の倫理規定が存在するし、守秘義務を守るのはいろはの「い」である。だが、言ったか言わないかではなくて、そういう懸念を一瞬でも抱かせてしまうこと自体がアウトなのではないか、相談業務の最前線にいてはいけないのではないかと、心がざわついた。
思いあまって先輩に相談した。実は翻訳の仕事をしていること、たまに書評などが載り、しょっちゅうではないけれど顔写真も表に出ることがあり、そうしたら、私というソーシャルワーカーに相談する人は、不安になるんじゃないでしょうか。こっちは現場離脱もやむを得ずの悲愴な覚悟だったが、先輩の答えは思いのほかあっさりしていた。
「気にし過ぎじゃない? だって、韓国の小説って売れてないでしょう?」
そ、そうなんだ……。私、かなりの自意識過剰人間に見えてしまったか。
確かに、「韓国文学」は10人いたら9人は読んでいる必読図書とは言えないかもしれない。念のため先輩に「あのう、『82年生まれ、キム・ジヨン』って知ってます?」と訊くとぽかんとされたので、それが「K-文学のヨン様」とも称される、2021年現在韓国文学最大のヒット作という事実は告げなかった。先輩は、迷惑さえかけなければ別にかまわない、やりたいことをどんどんやれ、せっかくだから大ヒット作を翻訳して! と、むしろ励ましてくれた。もやもやはさらに濃くなった。
仕方がないので、自分で工夫することにした。見た目を変えることにした。
といっても大したことはできないので、とりあえずソーシャルワーカーの時はコンタクトレンズを使用禁止にした。相談業務の時は、分厚いレンズにどでかいフレームのメガネ。コンタクトの私しか知らない相談者に気づいてもらえないことがたびたびあって、小さく安堵した。まあ、小手先である。小手先なんだが、できる努力はしておきたかった。というか、その程度の小手先しか思いつかなかった。どちらの職も手放したくなかった。
***
後編に続きます
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子