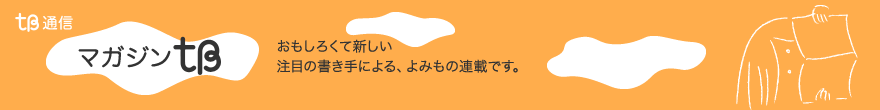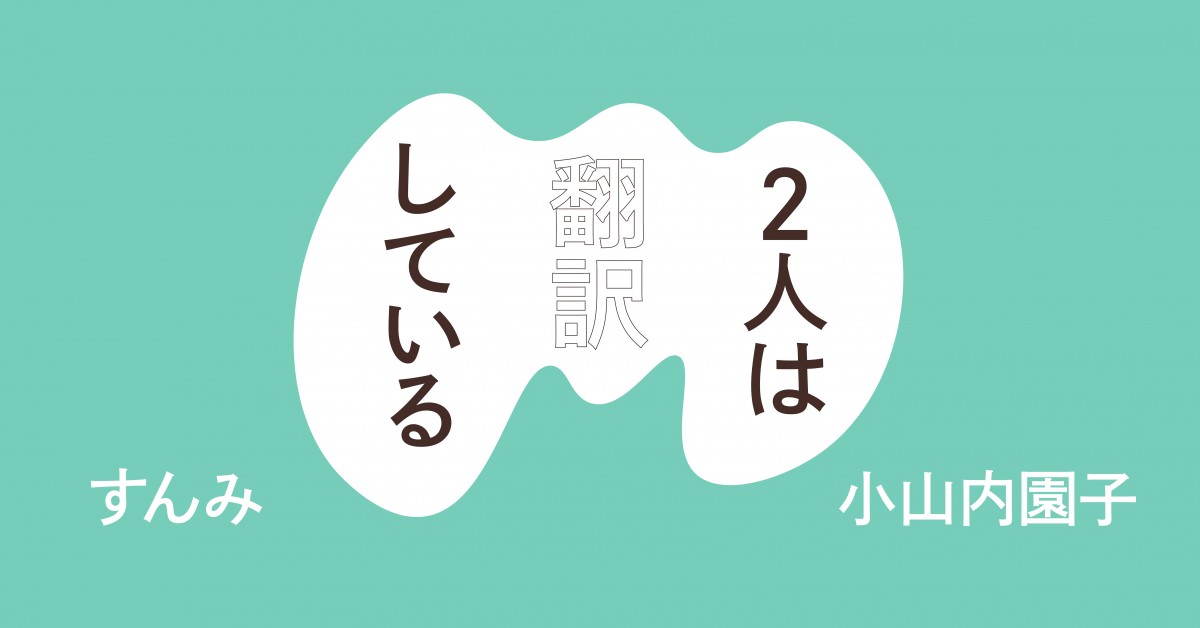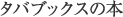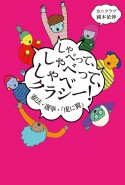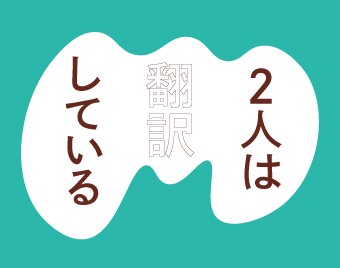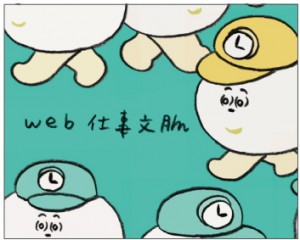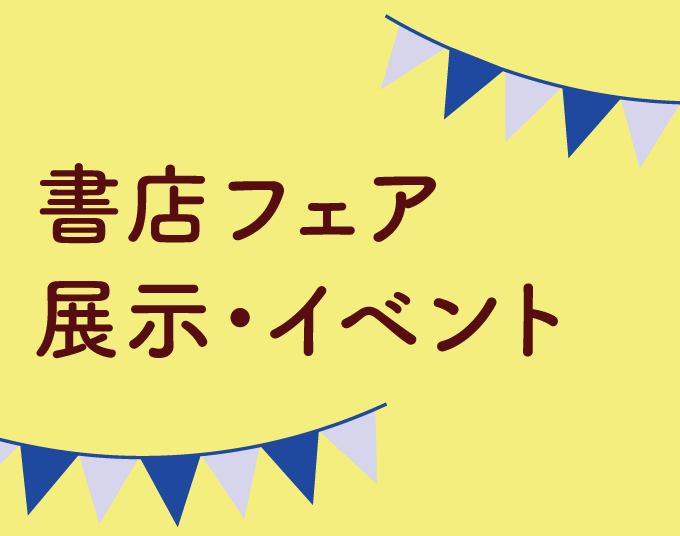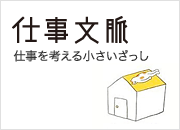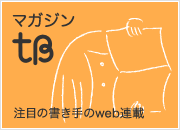ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
(2025/1/23)
翻訳において失われるものは、確かにあるかもしれない。
***
いきなりだが、私の第一言語は、津軽弁である。
津軽弁、ご存じだろうか。江戸時代に津軽氏が治めていた弘前藩、黒石藩の領域で使われる言葉。地理的には青森県の西部に当たる。ちなみに青森県では、津軽弁と南部弁の主に2つの方言が使われている。青森市出身の私は津軽弁だが、青森県東部の八戸市に住む親戚は南部弁で、両者が本気でなまりあうと、けっこう通じない。
地方に生まれたこと、それも、標準語とはかなり異なる営みを持つことばを使う地域に生まれたことについて、あまり深く考えたことはなかった。いや、自分で考える前に決まっていた気がする。「そのことばを使う人たち」の立ち位置は、中央=標準語を使用する人々によってとっくに規定されていて、それをごくんと呑みこまざるを得なかった。
たとえばテレビだ。青森に住んでいた1970~80年代、最も勢いがあるメディアはテレビだった。当時は地域によって民放の数に違いがあり、TBS、日テレ、テレ朝、フジという地上波の4大ネットワークそれぞれの系列局がある地域、つまり、地方局が4局以上ある地域は限られていた。私が小学生の頃、青森市は日テレ系列とTBS系列の2局しかなく、一方、当時キー局で断トツの人気を誇っていたのはフジテレビだった。すると何が起こるか。系列外の地方局が、フジテレビの人気番組を単体で購入して、別な時間帯に放送するのである。正午が放送時間の『笑っていいとも』は、夕方5時から放送されていた。「お昼休みはウキウキウォッチング~」で始まるオープニングテーマソングが、午後5時に流れる矛盾。しかし私もクラスメイトも、その現象に何の疑問も抱かなかった。〈ここは、トウキョウでお昼12時に放送する番組を、夕方の5時に見なければならないところ〉。そう呑み込んでいた。
「いいとも」だけではない。『新春かくし芸大会』も『カルピスまんが劇場』も。『小学〇年生』とか『明星』とか『ザ・テレビジョン』とかで特集される番組は、ことごとく放送時間が違う。そして、違うことが続くと慣れる。腹を立ててもどうしようもないことだからだ。
呑み込んだことは他にもあった。刑事ドラマや2時間サスペンスの場合、「やむにやまれず犯罪に手を染めた犯人」が青森出身、というパターンが少なくなかった。そしてその犯人たちは、大体が謎の津軽弁の使い手だった。
「オラあ、出稼ぎでここまできたべ。田舎に子どもらを残してきたのに、東京は冷てえ!」
刑事に追いつめられた犯人が、新宿の高層ビルが見える場所あたりで激白し始めると、わが家ではまず母が、「またか」という溜息をついて立ち上がり、晩酌中の父はコップにどぼどぼと日本酒を注いだ。そういう台詞が始まる時、大体オチはわが県だと予測がつくからだ。刑事が「お前、国はどこだ」と訊く。犯人が答える。「青森だべ」。
それほど青森に関心があるのなら、せめてきちんと方言考証すればいいのに、と今でも思う。上の犯人の台詞を、私の津軽弁で翻訳すればこうなる。
「わ、出がせぎでこさきたんだ。田舎さ、わらはんどばおいで来たのに、東京は冷てんだね」
本当に犯人の第一言語が津軽弁なら、そして、標準語を使う相手に方言で答える必然性があるなら(先に書いたように、子どもの頃から東京とは言語も時間軸も違うと呑み込んでいるので、わざわざ通じないかもしれない津軽弁を口にするより、標準語で答える可能性のほうが高いと思う。もっと言えば、刑事にタメ口というのもなかなかハードルが高い)、訳はこうなるし、そうすると、刑事も津軽弁話者でない限り、意味は通じないはずなのだ。だって津軽弁では、単数の「子ども」は「わらし」で、それが複数だと「わらはんど」なんだから。ほとんどドイツ語である。
だが、おそらくああいう設定は、本気で地方と首都の格差を描きたかったわけではないのだろう。なまっているとわかる、しかし偽物の方言で、その構造をエンタメにしたかっただけなのだろう。私が青森出身だと知ると、ごくたまに、わざわざ津軽弁風になまってみせる人がいる。もちろん津軽弁ネイティブではない。「テンポが面白いから言ってみたくなった」「なまりがすてきで」などと言いながら口真似をする。そういう時、何ともいえない苛立ちを感じる。故郷の言語を「なまり」と対象化されることへの怒りもあるが、習う気もない人間に、「おもしろい」響きだと消費されることに怒りを覚えるのだと思う。
方言が多用されている小説を訳すことが決まった時、まず頭に浮かんだのは、この津軽弁にまつわる記憶だった。マズいなあ、と思った。方言、しかも別の国の、特定の歴史と感情が積み重なった言語を、それとはまた違う歴史や感情の絡んだ日本の特定地域の言語に置き換えていいものだろうか。作品はすばらしく、ぜひ紹介したく、だから訳せるとなったときには大喜びしたのだが、いざ訳し始めて、その点に頭を抱えた。2024年最大のピンチだった。
***
後編に続きます
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子