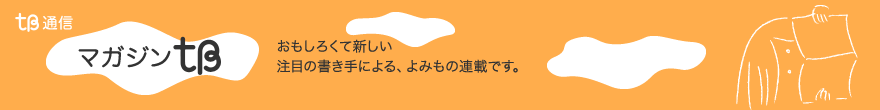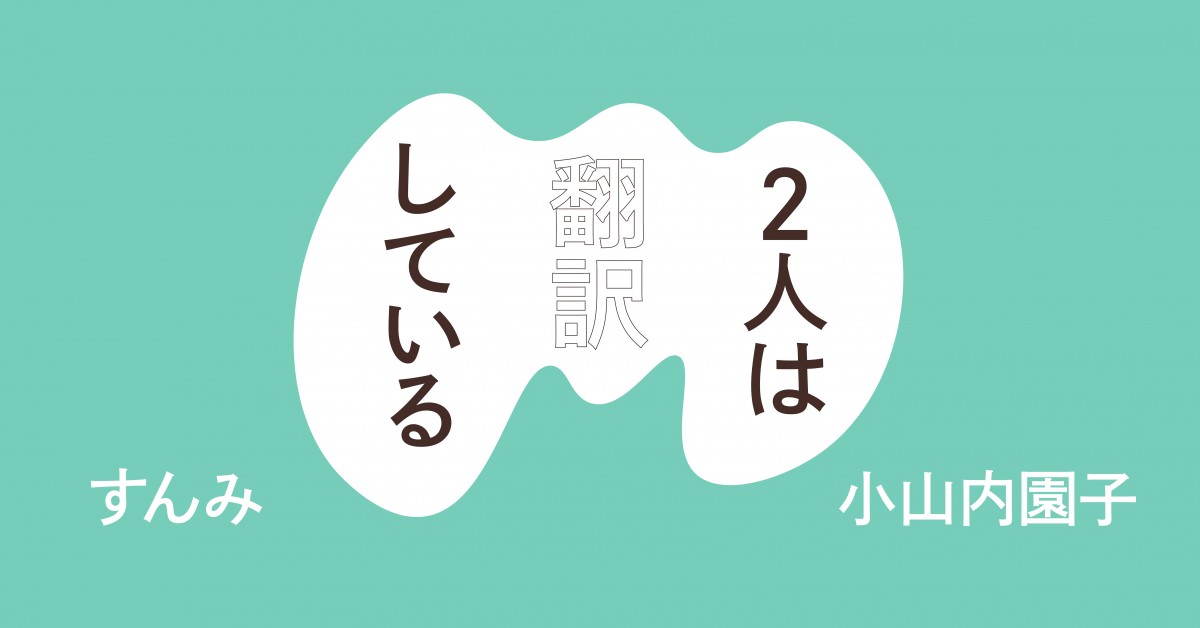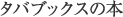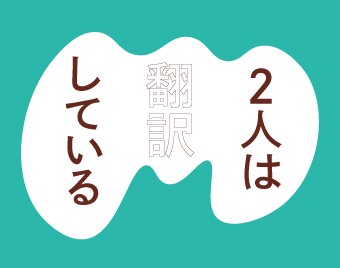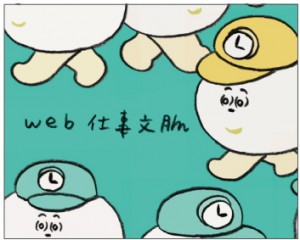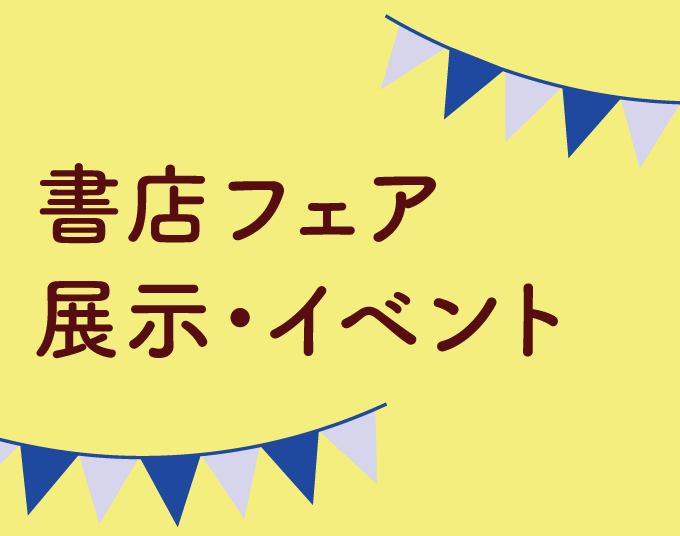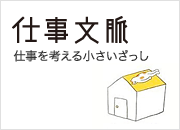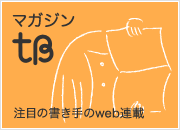新しい風景を求めて(後編)/すんみ
(2025/10/3)
前編はこちらです
*
小山内さんのコメントを確認していると、私に見えている作品の中の風景が変わってくる。
「風景」という言葉で思い出すのは、「もの派」として知られる美術家、李禹煥(リ・ウファン)の≪風景≫という三連作だ。国立新美術館開館15周年記念で行われた「李禹煥」でこの作品を初めて見た時の不思議な感覚は、今も忘れられない。
小さな部屋の三面に、それぞれピンク、赤、オレンジの蛍光塗料が塗られた巨大なキャンバスが三枚掛けられていた。一枚の絵を見て次の絵に目を移すと、最初の絵の残像が重なって見える。三枚の絵を見た時も、同じような現象が起きた。さらには部屋に入ってきた他の観覧客の顔までが、絵の残像に染まっていく。目にした色彩が周囲の空間に影響を及ぼし、風景を次から次へと変えていく。
展示会で買った画集に掲載されている「李禹煥≪風景≫(1986年)試論」という論考にはこう書かれている。「≪風景≫と題されているが、李が提示しようとしているのは作品の内側に現出する光景ではなく、作品が周囲におよぼす状況であり、鑑賞者を包み込む空間、環境の中で得られるはずのそれぞれの体験の内にある。したがって『風景』という題名から、字義通りの具体的なイメージを期待した場合、その期待は裏切られることになる」。この指摘通り、李禹煥≪風景≫の三連作は、私が持っている風景の概念を覆すものだった。
もしかしたら小山内さんとの共訳で、私はこのような感覚を求めているのかもしれない。作品を読んで私が見た風景を、打ち破ってくれる言葉を待っているのだ。私が小山内さんの担当分にコメントをつけて戻した際の反応を見る限り、小山内さんも同じような喜びを感じているような気がする。メールの文面から「そう来ましたか!」とニヤニヤする顔が思い浮かぶのだ。
最近の韓国文学を読んでいると、読みながら思い描いた風景が一変してしまう経験をすることがある。例えば、韓国SF作家のチョン・ソヨンの短編小説「おうち」。パートナーを、防ぐことができたはずの事故で亡くした宇宙飛行士の話だ。この話を初めて読んだ時、私はこれまで読んできた恋愛小説のように、男女の恋の話として読んだ。しかし、いざ訳すとなった時、あることに気づいてハッとした。どこにも性別を表すような言葉が書かれていないのだ。私が作品を読みながら見たのは、自分の先入観から生み出された風景だった。この事実に初めて気づいた時は、本当に驚いてしまった。私はこれまでたくさんの物事を、このようにして見てきたのだろう。
風景という言葉で思い出す日本文学がある。日本語とドイツ語で創作を続けている多和田葉子の長編小説『ボルドーの義兄』だ。ドイツ語で書いて発表したものを著者自身が日本語に翻訳したという。その経緯も面白いのだが、作品そのものも極めて独特だ。単行本の表紙には、「小説の見たことのないカタチ」と書かれており、ページを開くと鏡文字で書かれた漢字がまず目に留まる。
主人公の優奈は、「身に起こったことをすべて記録したい」と望み、「出来事一つについて漢字を一つ書」き留める。この漢字が、鏡文字になっているのだ。そしてその漢字一文字を「トキホグス」ことで、「たくさんのことが同時に起こりすぎる」「身に起きたこと」を記録していく。しかし、その記録された話は、鏡文字で書かれた漢字と直接的な関係がないことも多い。優奈がフランスのボルドーに滞在しながら、留学中のハンブルクでのことを振り返るという筋書きはあるものの、様々な考えや出来事が入り交じり、屈折しながら話は進んでいく。なんとも不思議な作品だと思った。
文庫版『雲をつかむ話/ボルドーの義兄』の解説を書いた文芸評論家の岩川ありさは、「門」というものを正確に捉えようとする優奈についてこう説明する。
優奈は言語によって世界を分節していることに気がつく。実際の建築物と漢字の「門」は同一のものではないにもかかわらず、避けがたく結びつき、優奈は物そのものを把握することができない。「本物の門」と漢字の「門」はなぜ結びつくのか。あるいは、実際の形と一致していないのか。(中略)「門」という漢字が示す内容は、実際に見える「門」から、概念的な「門」まで次々と移り変わる。
この説明を読んで、実は私たちも優奈のように世界を見て、記録しているのだろうと思えた。私たちは言葉によって世界を捉えようとするが、その言葉にはいろいろなイメージと概念が付きまとう。一つの言葉にも、この世にいる人の数だけの物語がある。その物語を、私たちはつねに「ホンヤク」しながら生きていかざるを得ないのだ。言ってみれば、私たちは誰もが翻訳者なのだ。
『ボルドーの義兄』にはこのような一文がある。「一度書きしるされた言葉は、それがどういう理由で書かれたかには関係なく、必ず未来に影響を及ぼす」。私たちはこれまで目にして、書いた言葉に、いつまでも影響されていく。言葉は何度もホンヤクされながら、私たちに新しい風景を見せてくれる。
大学生の時、多和田葉子さんのイベントのお手伝いをしたことがある。食事会で運よく隣の席になり、多和田さんの『ボルドーの義兄』の韓国語版を何人かがそれぞれ訳して同時に何冊もの翻訳版が出たら面白いだろうという話をした。多和田さんも私の妄想を面白そうに聞いてくださった。しかし、この記憶もまた、「夢」という文字からホンヤクされ、生み出された物語なのかもしれない。
(了)
すんみ
翻訳家。訳書にキム・グミ『敬愛の心』(晶文社)、チョン・セラン『八重歯が見たい』(亜紀書房)、ユン・ウンジュ他『女の子だから、男の子だからをなくす本』(エトセトラブックス)、ウン・ソホル他『5番レーン』(鈴木出版)、キム・サングン『星をつるよる』(パイ インターナショナル)、共訳書にチョ・ナムジュ『私たちが記したもの』(筑摩書房)、イ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(タバブックス)、ホンサムピギョル『未婚じゃなくて、非婚です』(左右社)などがある。
「2人は翻訳している」は今回最終回です。ご愛読ありがとうございました。
連載をもとに、書き下ろしを加えた書籍を準備中です。
11月下旬に刊行予定です。どうぞよろしくお願いいたします。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子