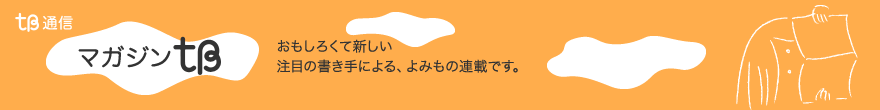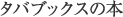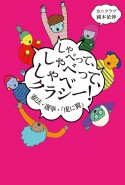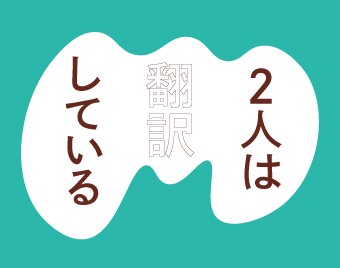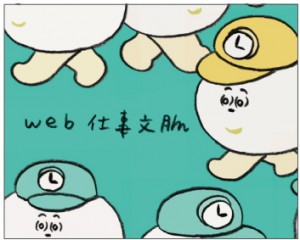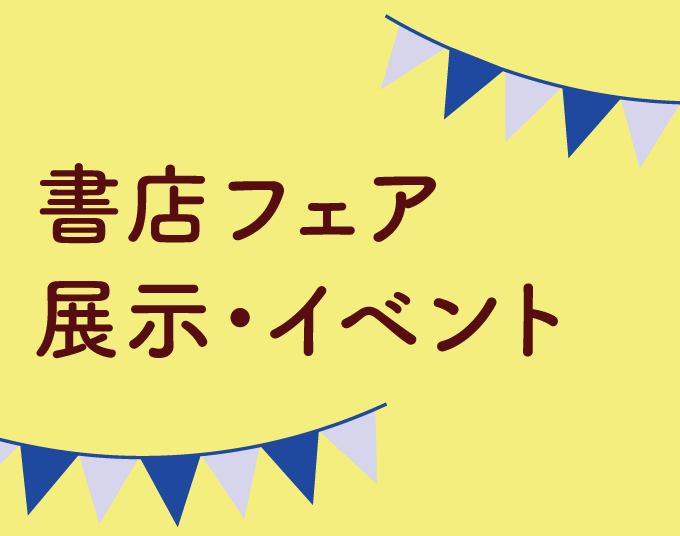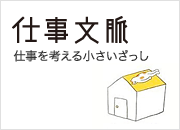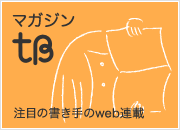青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
(2025/6/10)
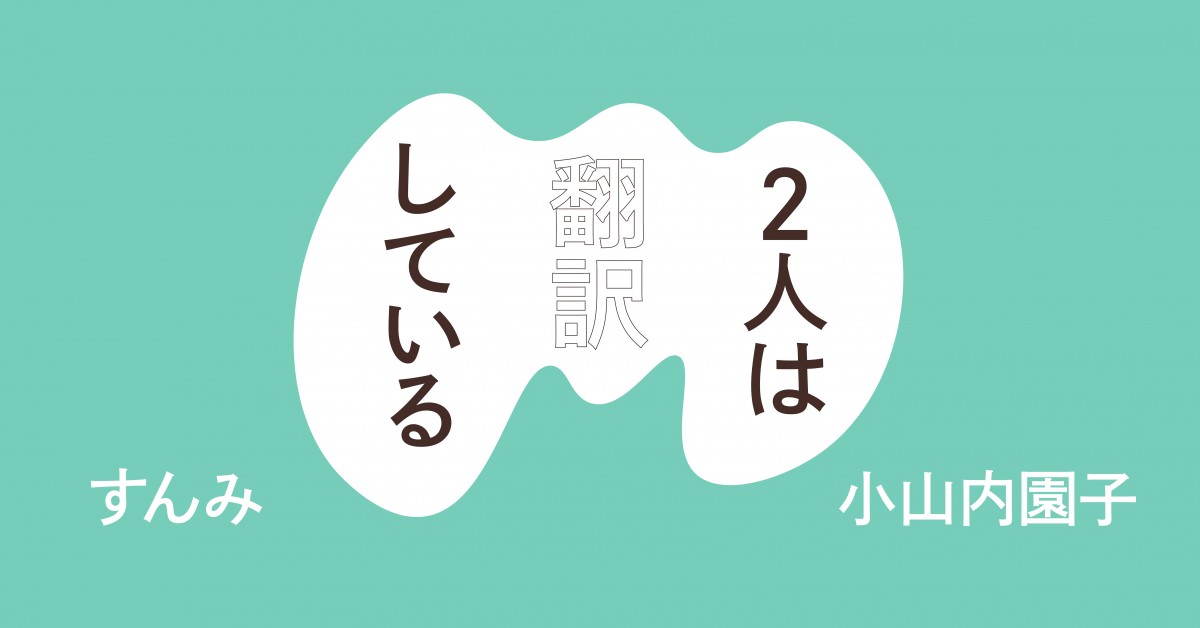
前編はこちらです
**
時間と距離を置こうとして以来、不思議な感覚に襲われるようになった。言葉を信じられなくなったのだ。どんな言葉にも実体を感じられず、どれもが虚偽のように思え、虚無感に襲われた。他人の話だけでなく、自分の発した言葉からも同じような感覚を受けた。「どうせ嘘だろう」という感覚が離れず、苦しんだ。
その時は、なぜ言葉が信じられなくなったのか理解できなかったのだけれど、今思えば、それは私が時間の流れを信じられなくなったことと関係があったのかもしれない。
先日読んだ小山内さん訳のイム・ソヌの短編集『光っていません』でも、登場人物たちは極限の状況に追い込まれ、時間が止まったかのような喪失感に包まれていた。ところが、この登場人物たちには、不思議な現象が起き始める。まるで幽霊のような分身との共同生活が始まったり、人間がクラゲや木などに変身したり。読んでいて心地よいのは、この摩訶不思議な変化は、絶望的なものではなくて、むしろ「自分が属している別な世界がある」ということへの気づきをもたらすような、そんな変化だからだ。それは、登場人物たちを止まってしまった時間から救い出し、前を向いて新たなステージへといざなってくれるような、そんな変化だ。そう、「変化」とは「時間の流れ」そのものとしてあるのだ(東京新聞6月10日夕刊に本書書評を書いているので併せてご覧ください)。
「ちょっと見ないあいだに大きくなったね」とか「お前もだいぶ老けたな」とか。人は、「変化」を感じた時に、時間の流れを実感する。そういえば、『敬愛の心』の敬愛に、時間の流れを感じさせてくれるものは、徐々に成長していく植物だった。また、日本の作家、古井由吉の作品では、部屋に閉じこもって物思いに耽ったり、本を読んだりしている登場人物が、四季の移ろいから時間の流れを感じている。
ビフォーアフターの落差が大きいほど、長い時間の経過を推察できる。30年前はこんなに若かったのになあ、と。しかし、短時間で大きな変化や落差を実感すると、それは事件となる。東日本大震災では、あのたった数十秒で、世界が一変してしまった。大事件だったのだ。もちろん、30年、50年かけて、大きく変化していくこともある。水の流れが数万年、数十万年を費やしてつくりあげた巨大な鍾乳洞などは、その緩やかな変化の中に、悠久の時を感じる。これもまた一つの事件だ。『光っていません』では、まさにこうした事件としての自分の変化を感じさせられることで、人物たちの時間は流れ始めるのだろう。そして実はこの変化と時間というものは、言葉を使う時にも生じていることなのだ。
翻訳をしていて強く感じるのは、何かを言葉にしようとする時、そこには必ずタイムラグがあるということだ。韓国語で理解したことを、日本語に変換する。そのプロセスが、確かに自分の中にタイムラグを生む。母国語で、無意識のうちに言葉を発する時には得られない感覚だ。そしてそのタイムラグは、何か言おうとしていたことと、結局言葉で言い表せたこととを、否応なく変化させてしまうものでもある。あれでもないこれでもないと考えているうちに、その時間は、翻訳した言葉で表せた意味を、元の意味から少し変えてしまうのに十分な時間となる。
翻訳だけでなく、母国語で言葉を発する時にも、実は感じられないほど一瞬のタイムラグが生じる。むしろ、その時間的な差こそが、「言い表そうとしていること」を「言葉」に変換することを可能にしているのだろう。それは変化なのだから、そこには時間が流れている。時間の流れがなければ、何かを言葉に変換することもできない。私の時間が止まった時、私は、何かを言葉に変換する時間も失っていたのだろうと思う。
時間の流れが受け入れられるということは、変化も受け入れられるようになったということだ。息子が生まれ、どんどん成長していき、慌ただしくあれこれと過ごしているうちに、変わっていくことは当たり前のことになっていった。「時間が解決する」という言葉がある。事件が起きて、言葉を失ったとしても、時間は否応なく流れていく。止まったように感じていても、実は時間は流れている。その時間の流れは、自分をいつのまにか変化させている。一度失った言葉も、いずれ戻ってくる。自分の日常を言葉にして、実感することができるようになる日が、いずれ訪れる。
この間、川岸を一緒に散歩中だった母が、突然歌を歌い出した。「青山(せいざん)は私に、黙って生きるようにと言った」というような歌詞だった。何の歌か尋ねると、母は仏教讃歌だと言い、結婚してから兄と私が成人するまで、人に言えないような苦しみを抱えていた時、この歌をよく歌ったと教えてくれた。母が言葉を失っていた三十年という長い時間が、その歌に乗ってようやく流れ出しているように感じられた。
すんみ
翻訳家。訳書にキム・グミ『敬愛の心』(晶文社)、チョン・セラン『八重歯が見たい』(亜紀書房)、ユン・ウンジュ他『女の子だから、男の子だからをなくす本』(エトセトラブックス)、ウン・ソホル他『5番レーン』(鈴木出版)、キム・サングン『星をつるよる』(パイ インターナショナル)、共訳書にチョ・ナムジュ『私たちが記したもの』(筑摩書房)、イ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』(タバブックス)、ホンサムピギョル『未婚じゃなくて、非婚です』(左右社)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子