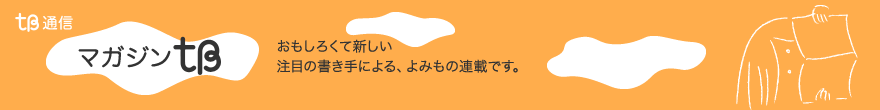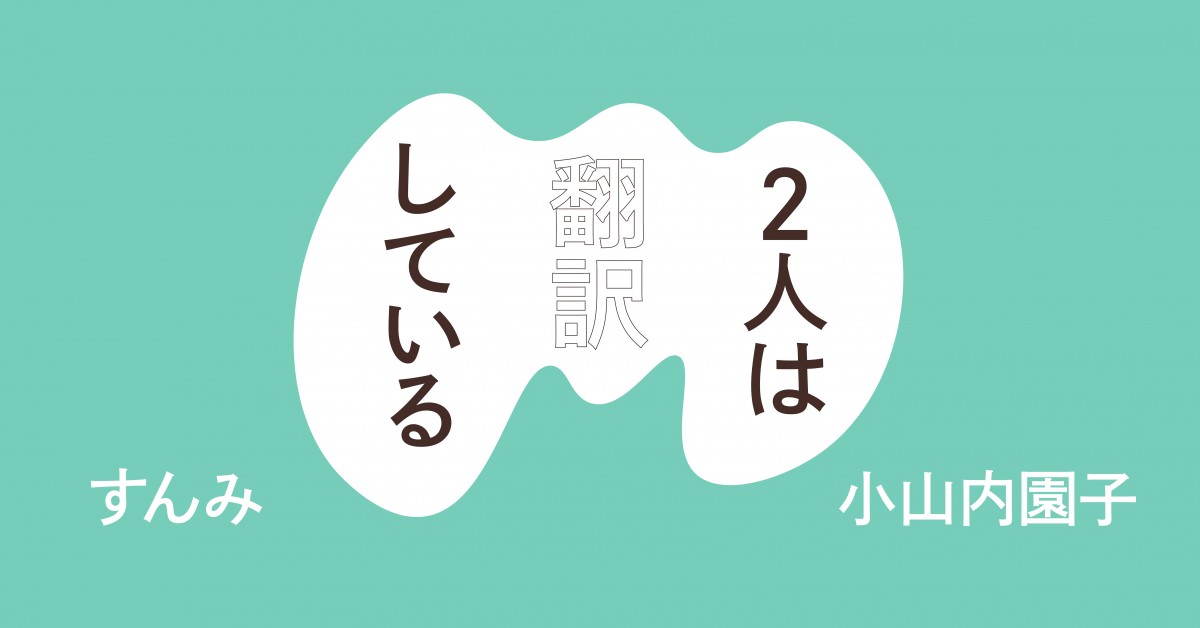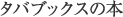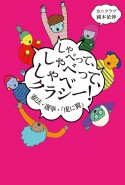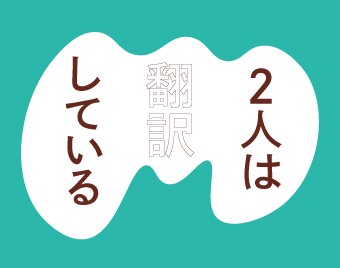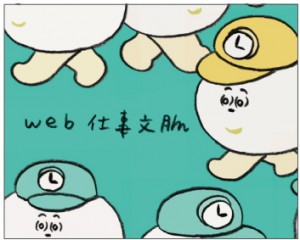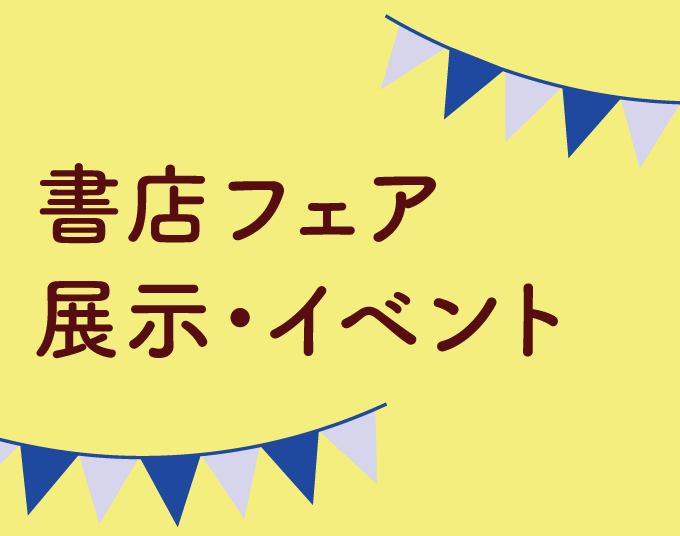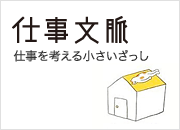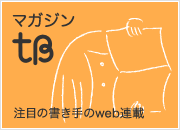ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
(2025/1/24)
前編はこちらです
***
当然だが、韓国にももちろん方言はある。
2024年にノーベル文学賞を受賞した小説家、ハン・ガンの最新長篇小説『別れを告げない』に登場するのは、済州語と呼ばれる言葉だ。同年冬に公開された映画『対外秘』で登場人物たちが口にしているのは釜山のそれ。日本同様、方言によっては単語そのものが異なり、標準語から意味を類推するのが難しいものもある。
私が翻訳を担当することになった作品は、慶尚道(キョンサンド)という地域の方言だった。朝鮮半島南東部に位置し、釜山(プサン)、蔚山(ウルサン)、大邱(テグ)という3つの広域市を擁する土地。主たる産業の1つは農業で、主人公の高齢女性が住む地域の特産品はリンゴである。そんな自然豊かな環境で、彼女は訳あって、自分の手で孫を育てている。そして最近、その小学生の孫との言葉の通わなさに、もどかしさを抱えている。SNSを通じてどんどん知らない世界に踏み込んでいく孫に、言い知れない不安を抱く。
物語の中で、主人公が必死に紡ぐ方言は、孫との間にそびえたつコミュニケーションの壁の象徴のように思えた。また、ソウルことば(서울말:ソウルマル)との語感の違いが、標準的でないがゆえに切り捨てられてしまう存在の孤独を漂わせている。方言は、明らかにその作品を構成する重要な要素だった。
……と、そこまではわかるのだが、じゃあいったい、どう訳したらいいんだ?
まずは、韓国の方言を日本の方言に置き換えることを考えた。前述の『別れを告げない』で、訳者の斎藤真理子さんは済州語を沖縄語に訳出している。島という環境、非常に残酷かつ不当な戦火に巻き込まれた歴史を考えた時、その選択に唸った。膝を打った。翻訳は常に選択の連続だけれど、斎藤さんはどのタイミングでこの決断をしたんだろう。原文を読んでなんとなくイメージがついたのか。それとも悩みに悩んだ末、ある種の苦渋の選択だったのだろうか。
悩みに悩んだ末、方言を方言として訳出しなかった訳者もいる。たとえば、映画監督としても有名なイ・チャンドンの短編集『鹿川(ノクチョン)は糞に塗れて』の訳者、中野宣子さんは、作品の方言を標準語の日本語で訳出している。収録作品「龍泉ペンイ」の中で、こんな訳注を読むことができる。
「日本語のどこの方言であれ韓国語の方言の正確なニュアンスは伝わらないと考え、共通語で訳す」(p.48)
なるほど、確かに。方言を別な方言に置き換えるという作用は、場合によっては劇薬になる。たとえば、ネットで「釜山/方言/日本」と検索すると、「釜山弁は日本の関西弁に似ている」というわかりやすい説明がヒットするが、だからといって吟味なしに置き換えれば、先入観の拡大再生産につながるだろう。青森出身の犯人に謎の津軽弁を駆使させていたあのドラマなど、明らかに「吟味なしの先入観拡大再生産装置」である。いくらこの地域が釜山に近いからとって、関西弁に訳してしまったら、物語の何かが失われる予感がした。
いや、待てよ。そもそも、私が原文の慶尚道方言を正しく読み取れているかどうかからして、まずチェックが必要なんじゃないか? 私はその言語を体験していない。誤読をしている可能性は十分ある。早急に慶尚道の方言に詳しい人を探して、手伝ってもらわなくては。いるだろうか? そんなありがたい人が。私は再び頭を抱えた。
結果として、そんなありがたい人はいた。とても身近に。自分でも、少し出来すぎだろうと思った。すんみさんだった。方言に限らず、長く翻訳の相談にのってもらっている仲間。ニュアンスまで共有し合える人。途端にやる気になった私は、すんみさんの迷惑も顧みず、細かいことまで質問しまくった。そんなやりとりの中で、すんみさんが慶尚道の方言の具体的な用例を1つ、教えてくれた。
「ちなみに、가가 가가가(カガ カガガ)は、あの子がガさんなの、って意味です」
え? それって、私の故郷の言葉をネタにするときの、あの用例と似てないか?
「どさ?」「ゆさ」(「どこに行くの?」「温泉に行きます」)
考えてみれば、一文が短いところや音数が、津軽弁に似ていた。認知度の高い関西弁のような方言とは違う、一瞬どこの言葉なのか、何を言っているのかと、相手を戸惑わせるような固有さも。全く同じではないとしても、物語を損なわない選択のような気がした。
訳者が自由に使える方言が津軽弁だから、という理由でだけは、決して津軽弁で訳出すまいと決めていた。そもそも世界には、翻訳できない言葉がたくさんあるのだから。しかし、共通点が複数あって、その選択を人に説明できるのであれば、恐れずやってみてもいいのではないか。そういえば著者はインタビューでこう言っていた。自分の作品の特徴の1つが、方言だと。
そんなわけでこの作品は津軽弁で訳出するという判断を下している。とりあえず、今のところは。
***
年明けに、家族がサブスクで映画『ロスト・イン・トランスレーション』を観ていた。横目で見ながらふと、タイトルに「トランスレーション」が入っていることに気がついた。lost in translation――「翻訳において、失われる」。原文を必死に再現したくても、翻訳はいつも、何かを、失っているのかもしれない。だけどひょっとしたら、意味を豊かに重ねて世界観をふくらませる翻訳というのも、ありえるのでは? 一縷の望みを抱いて、今私は、どちらかというと津軽弁のほうを勉強し直している。
前編はこちらです
小山内園子(おさない そのこ)
韓日翻訳者。NHK 報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など。すんみとの共訳書にイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(タバブックス)などがある。
2人は翻訳している 一覧
- 新しい風景を求めて(後編)/すんみ
- 新しい風景を求めて(前編)/すんみ
- ささやかな「物語」に耳をすませる(後編)/小山内園子
- ささやかな「物語」に耳をすませる(前編)/小山内園子
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(後編)/すんみ
- 世界へ踏み出すための、新しい地図(前編)/すんみ
- 翻訳ができる体(後編)/小山内園子
- 翻訳ができる体(前編)/小山内園子
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(後編)/すんみ
- 青山は私に、黙って生きるようにと言った(前編)/すんみ
- 「今でもあなたは、わたしの光」(後編)/小山内園子
- 「今でもあなたは、わたしの光」(前編)/小山内園子
- しかたないという問題について(後編)/すんみ
- しかたないという問題について(前編)/すんみ
- ロスト・イン・トランスレーション(後編)/小山内園子
- ロスト・イン・トランスレーション(前編)/小山内園子
- 日本カルチャーという居場所(後編)/すんみ
- 日本カルチャーという居場所(前編)/すんみ
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(後編)
- 番外編 イ・ミンギョンさん講演会「韓国フェミニズムの〈いま〉」(前編)
- 参考書は『ガラスの仮面』(後編)/小山内園子
- 参考書は『ガラスの仮面』(前編)/小山内園子
- 私の「オンニ」史(後編)/すんみ
- 私の「オンニ」史(前編)/すんみ
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(後編)/小山内園子
- 翻訳者を友人に持つことの醍醐味(前編)/小山内園子
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(後編)/すんみ
- 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話(前編)/すんみ
- 翻訳の戦慄と陶酔(後編)/小山内園子
- 翻訳の戦慄と陶酔(前編)/小山内園子
- 2人は翻訳している すんみ/小山内園子